無機質な灰色のキーボードの上を、乳白色の指先が軽やかに滑る。
カタカタカタッ、カタタッ、カチャカチッ、タンッ!
エンターキーを打つ瞬間だけ一際強く小指に力が入る癖を、彼女は気づいているだろうか?
まるでピアノでも奏でているような彼女の優雅なタッチタイピングを横目に、寺嶋は不埒な想像を巡らせる。
彼女のほっそりとした指が自分の浅黒い肌を這い回り、うっすらと汗の滲んだ胸板に柔らかな紅唇が圧しつけられる様を。
寺嶋桂司が初めて彼女――佐野絢子を〝女〟として意識したのは、その横顔の、あまりの艶めかしさに気づいた時だった。
ディスプレイに向けられる伏し目がちな眼差しは、真剣なのに何処かおぼろげで、ふっくらと小ぶりな唇から時おり細い吐息が漏れる。開いたか開かないかの、ほんの僅かな隙間から……。
「どしたの、佐野さん? 悩ましげに暇そうだね」
胸中の欲望を軽口に変えて、寺嶋は、数分前からキーボードを打つ手が止まってしまっている絢子に声をかけた。
「悩んでますけど、暇ではないです」
グロスを塗った艶やかな唇をアヒルのように歪ませて、彼女が抗議の視線をよこす。
「寺嶋さんから押し付けられた、この重クレームのお客さん、どうやって謝ったら解決するか、作戦練るのに忙しいんです」
きっぱりと皮肉られ、寺嶋は苦笑した。
現在の時刻は、午後八時二十分。
午前十時から午後七時までの実働八時間勤務の彼女が、本来、会社に居残っているべき時間ではない。
現に、広さ六十畳のオペレータールームに残っているのは、寺嶋と絢子の二人きり。他の人間は、とっくに退勤してしまっている。
「押し付けたんじゃないよ。佐野さんに任せれば大丈夫だと思うから、お願いしたんだ」
「どっちにしても、やる事は同じじゃないですか」
あからさまに不平をこぼしつつも、絢子は与えられた仕事を投げ出したりはしない。やがて意を決したようにヘッドセットをつけ、左手でテンキーを叩くような要領で電話番号をプッシュする。
「――様のお宅でしょうか? 夜分に恐れ入ります。ラグジュアリー・プレイスの佐野と申しますが――」
絢子の電話応対の一部始終を、見るとはなしに見守りながら、寺嶋は己の中の暴走気味な感情を持て余していた。
寺嶋がSVを務める「お客様サービスセンター」は、ダイニングボードなどの大型家具から箸置きの一つまで扱う総合インテリアショップ、ラグジュアリー・プレイスの問い合わせ窓口である。
客の希望に合わせた家具の配送日の調整、運送会社への連絡、はたまた製品不良の謝罪と、それに伴う交換手配……雑多で神経を使うコールセンター業務は、ストレスが溜まりやすく、従業員の流動が激しい。ぶっちゃけた話、客の理不尽な要求や、怒りの捌け口とされるオペレーターは、多かれ少なかれ何かしらの形で精神を病み、ベテランになる前に殆どが辞めていってしまう。
それもこれも、クレームになるような粗悪品の販売を許している上層部に問題があるのだが、いくら提言しても全く届かないばかりか、会社の方針に逆らう要注意人物として疎まれる現実を悟ってからは、一気に改革するのは諦めて、少しずつ自分の出来る範囲から改善していこうと、寺嶋は割り切っている。
だが、そう簡単に割り切れない人間は多い。
「――ええ、はい……はい……誠意……でございますか?」
戸惑い気味の絢子の鸚鵡返しを聴き、寺嶋は素早く内ポケットからボールペンを取り出し、手近にあった付箋に走り書きした。
『クッション&カバー、×2セット プレゼント 好きな色選ばせてOK』
無言で絢子の前にメモを差し出し、顔を上げた彼女に頷いてみせる。それを目顔で受けた絢子は、落ち着いた口調に戻って会話を続けた。
「かしこまりました。もし、ご迷惑でなければ、お詫びの気持ちといたしまして、クッションとカバーのセットをプレゼントさせていただければと存じますが、いかがでしょうか? ……はい、もちろん、お好きな色をお選びいただいて結構でございます――」
どうやら、上手く話がまとまりそうな気配を感じ、寺嶋はほっとした。
エンドユーザーに対するクレームの対応というものは、クライアントとの商談よりも遥かに手強い交渉と言える。感情的になっている相手を宥めすかすのはもちろんだが、自分たちの非が明確である場合、謝罪をしながらも、客の言い分に引きずられてはならないからだ。サービス精神は重要だが、所詮は商売。出来る限り、損失を抑えるのが絶対条件である。顧客満足度とコストの折り合いをつけながら、最低でも赤字にならないラインで話をまとめるのは、決して簡単なことではない。
まして、客に対する誠意が強ければ強いほど、会社の経営方針との板ばさみになり、心が荒む。
「――ご迷惑をおかけ致しまして、誠に申し訳ございませんでした。今後、このような事のないよう、改善に努めて参りますので……え? あ、いいえ、とんでもないです。……はい、ありがとうございます。それでは、失礼いたします」
パソコンのディスプレイに向かって深々と頭を下げ、絢子は沈黙した。電話口の相手が受話器を置くのを確かめて、ヘッドセットを外す。そして、沈鬱な溜息を一つ。
「はぁー……」
「お疲れ」
心底うんざりした様子が伝わってくる彼女の溜息に、寺嶋は労いの声をかけた。絢子は、明らかに割り切れていない人間である。それを知りながら、彼女にクレーム処理を任せているのは、寺嶋自身、かなり引け目を感じている。だから、出来る限りのサポートはしてやりたいと思っている。
「もう、嫌です」
疲れた顔をして、絢子は低く呻いた。
「今のお客さん、すごくイイ人で、最後なんか『あなたが悪い訳じゃないのに、無理言って悪かったね』って同情までされちゃいましたよ。この居た堪れなさを、ぜひとも商品開発と品質管理の連中に味わわせてやりたいです……」
ついでにバカ社長にもな。
心の中で、寺嶋は付け足した。絢子の気持ちが痛いほどわかるだけに、遣る瀬なさが胸を塞ぐ。立場は違えど、会社の方針と、部下たちに下さなければならない、己の意に染まぬ命令の間で苦しんでいるのは、寺嶋も同様だった。
「ああ、もう、ほんっとヤダ!」
寺嶋へ、というよりは独り言のようにぶつぶつ言いながら、絢子はデスクに突っ伏した。その瞬間、サラと流れたセミロングの黒髪に、寺嶋は、優しく指を絡める自分の姿を思い描く。
重症だ。
どうして、こんなにも強い欲望を覚えるのか、寺嶋は自分で自分が判らない。無論、誰に対しても同じような感情を抱く訳ではない。
欲しいのは佐野絢子、ただ一人――。
元々寺嶋は、絢子の事を異性としてではなく、優秀な部下として、高く評価していた。
寺嶋が絢子に一目置くようになったのは、彼女の今時の若い女にしては珍しい、澄んだ優しい声のトーンと、落ち着きのある言葉遣い、そして何より、天賦の才とも思えるクレーム処理能力の高さからだった。
おまけに、根が真面目で誠実で、上司の目が有ろうと無かろうと、いつでも一生懸命に仕事をこなす。その裏表のない健気さが、何より寺嶋の気に入った。
この人間は信用するに値する、自分の片腕になる――という確信を得てからというもの、寺嶋は、難易度の高い仕事を中途採用のパート社員に過ぎない絢子にそれとなく回し、周囲に悟らせること無く、少しずつ彼女を鍛え上げてきた。
だが、周りの人間は気づかなくとも、当の本人がいち早く気づいてしまった。
『寺嶋さんが持ってくる案件って、いつもロクでもないのばっかりで、嫌なんですけど』
ずばり言い当てられた時には、答えに窮した。そして、正直に打ち明けてしまったのだ。その内、正社員に登用してサブリーダーに抜擢したいと考えている、と。
それを聞いた絢子は軽く眉をひそめ、私は一オペレーターで満足してます、とハッキリ拒絶したものだった。正社員なんて肩書きも、責任ある立場も欲しくないんです、と。
その時の、ふと背けた彼女の厳しい横顔と、物言いたげな唇を見た瞬間から、寺嶋の中で、絢子は特別な人間に変わった。
何処がどう、というはっきりした理由などない。
見えない罠に嵌ってしまったかのように、彼の心は囚われたままである。
絢子が欲しい。
ただ、その一事を願うだけ――。
半ばぼんやりと、そんな事を思い返していた時だった。
「――私が欲しいんでしょう?」
いつの間にか身を起こしていた絢子の黒目がちな瞳が、じっと寺嶋を覗き込んでいた。
「え?」
胸の内を見透かされたとしか思えないタイミングで放たれた言葉に、寺嶋は息が止まるほど動揺した。どう誤魔化したら良いのか、パニクりかけた寺嶋に構わず、絢子は投げ遣りな口調で続けた。
「だからー、寺嶋さんは、都合の良いクレーム処理係としての私が欲しいんでしょう? 他の同期の子たちは他部署に異動させてもらってるのに、私ばっかり、入社してから一年半、ずーっと寺嶋さんの下でクレーム地獄から抜け出せないなんて、イジメじゃないですか」
その、自分が危惧したのとは全く違った彼女の言い分を聞いて、寺嶋の頬に、思わず安堵の笑みが浮かんだ。
「うわ、今、笑いましたね?」
それを目ざとく見つけた絢子が露骨に顔をしかめる。感じ悪っ、と、とても上司に対する発言とは思えない悪態を吐く。
その無謀なまでの正義感、反骨精神が、自分と良く似ているのだと気づいたのは、彼女を愛し始める前だったのか、後だったのか。
「まあ、そんなこと言わないで、いつまでも俺に付き合ってよ」
寺嶋はにっこり笑って、それから、ぐっと声を落として囁いた。
「俺の下にいる限りは、トップが何と言おうと、顧客第一、貫いていいから」
大きく目を見開いた絢子に、おどけたように肩をすくめてみせる。
「その代わり、俺と一蓮托生。出世は諦めてね」
現在、三十二歳の寺嶋自身、自分の出世街道が果てしなく難所に満ちている事は十分認識していたし、だからこそ、イマドキ化石の世襲社長を本気で退陣させてやると、入社当時から密かに決意していた。こんな馬鹿みたいな会社に自分の人生を賭けるなら、とことん闘って、マトモな会社に改変するしか、やる甲斐が無いではないか。
その途端、絢子のクールな表情が、我が意を得たりとばかりに笑み崩れた。
「それじゃあ仕方ないですね。万年サブリーダーに甘んじますよ」
一度は断られたプロポーズ。
「――でも、私、寺嶋さんとなら、同じ蓮の上に乗っても大丈夫な気がします」
悪戯な微笑が、彼女の容良い唇を彩る。
一蓮托生。
自分から言い出した言葉ながら、寺嶋は、その意味の重さに今更ながらはっとした。
自分が望んだ人間が、自分と同じ価値観と目的意識を持って、共に戦場に立ってくれる。命運を共にしてくれるという。
これほどの幸福が、他にあるだろうか?
「サンキュ」
不覚にも目頭が熱くなりかけて、寺嶋は慌ててソッポを向いた。
「さー、帰ろ!」
感傷的な雰囲気を壊すかのように、絢子は、すっくと立ち上がり、大きく伸びをした。小首を傾げて、トントンと拳で肩を叩く仕草に疲労がにじみ出ている。
「佐野さんって、今、いくつだっけ?」
「肩なんか叩いて、年寄り臭いとでも思ったんですか?」
寺嶋の問いを絢子は質問で返した。
「違うよ。若いのに人間できてるなーって、感心しただけだよ」
本当は、彼女を採用した際に履歴書を見ているので、先月、二十八歳になったばかりである事は知っていた。
ただ、何となく彼女自身の口から聞いてみたくなっただけだ。
「だって、私、もう若くないですもん」
それとは知らず、すねたように唇を尖らせた絢子は、少女のようにあどけない。その表情に抱くのは、先刻までの欲情よりも遥かに手に負えない、狂おしいまでの愛しさだけだ。
「ところでさ、佐野さん、一蓮托生の意味って、ちゃんとわかってる?」
「それくらい知ってますよ、失礼な。結果がどうであれ、行動や運命を共にするって事でしょう?」
「うん、それもある。でも、この言葉って、本来は仏教用語なんだよ。死後、極楽浄土へ往生して一つの蓮の上に生まれ変わる事を意味してるんだってさ」
「……それって、死んだ後も一緒に暮らせる……って事ですか?」
絢子の声のトーンが微妙に落ちた。
「いや、正確に言うと違う。どれだけ現世で憎しみあった人間同士でも、死後の世界では、一つ蓮の上に生まれ変わって、かつての愛憎も超越して、共に幸福でいられるって事らしいから」
深いよね、と言って、寺嶋は絢子の表情を見守った。
ふーん、と相槌を打った彼女は、少しだけ考える顔になり、ぼそりと呟いた。
「私は、好きな人とだけ一緒の蓮で暮らしたいですね――」
現世でも、来世でも。
その瞬間、二人の視線が絡まった。ほんの、一瞬だけ。
「俺も」
滲み出そうになる微笑みを押し殺して、寺嶋はぶっきらぼうに同意した。
言葉にして伝え合った訳ではないが、それで十分だった。
「佐野さん、これから何か用事ある? 昇進祝いに、一杯おごるよ」
「お祝いー? 名ばかり管理職の仲間入りを果たした、残念会の間違いじゃないんですか?」
「何だ、バレてた?」
「やっぱりー」
ほんの少しだけ親密になった空気を、いつも通りの軽口で混ぜ返し、二人はフロアを後にした。
明日から、何かが変わるという確かな予感を抱きつつ。
頼りなき浮世の蓮も、共に揺蕩えば、いつかは楽園に到ると信じて。
終 - 2008.03.26 -
INFORMATION
『一蓮の上で君と揺蕩えば』は、いかがでしたか?
よろしければ、感想をお聞かせ下さい。一言感想、大歓迎です!
あなたの愛ある一言が、作者の原動力になります!
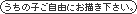
うちの子も、ぜひ描いてやって下さいまし☆ ⇒
絵板