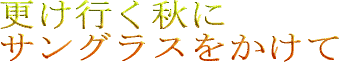Written by Ao Kamisawa.
第 1 話 一之瀬
彼の名前が〝一之瀬 〟であることは、認識していた。でも、下の名前までは知らない。
しょせん、アタシと彼の関係は、その程度のものだ。
「――四七二円になります」
ろくに人の顔も見ずに言うと、一之瀬は商品をビニール袋につめ始めた。
愛想のカケラもない奴――と、最初は思った。でも、何度か会計をしてもらっているうちに、気がついた。ないのは〝愛想〟ではなく〝余裕〟なのだと。
現在の時刻、二一時二四分。
繁華街の裏通りにあるこのコンビニは、ちょっとした穴場だ。裏と言っても全く人通りがない訳ではなく、ちょっと歩けばオフィス街に出るし、近くには大きな公園もある。そこそこの立地条件だと思うのだけれど、いつ来ても空いていて、レジを待たされた試しがない。
もっとも、アタシが行く時間帯だけが、たまたまそうなのかもしれないけど、おかげで周囲を気にせず立ち読みができるし、長時間コピー機を占領しても誰に迷惑をかけることもない。
アタシは千円札を無言でカウンターに置き、一之瀬の手元を見つめた。
若い男性の割には、繊細で美しい指をしている。一本一本が長くて、ちょっとした動作も綺麗だ。
でも、とろい。
紙パックのミルクティー、カレーパン、ミニサイズのグリーンサラダとシュークリーム。たったこれだけのアイテムをつめるのに、ゆうに三〇秒はかかる。
スピードが勝負のコンビニエンスストアである。気の短い客なら、早くしろ、と文句の一つも言うだろう。
アタシの見る限り、一之瀬はバーコードを通し終えた商品を〝袋につめる〟という作業だけが、不得意のようだった。
重いもの、軽いもの、柔らかくつぶれやすいもの、はたまた、冷たいもの、温かいもの。数々の雑多な商品を、その特性を損ねることなく、いかに効率よく収納するかに頭を悩ませている。
ようやく商品を入れ終えた一之瀬が、ほっとしたように顔を上げた。
卵型の優しい輪郭に、二重の大きな瞳。男らしいシャープな鼻筋と、ふっくらと立体的な唇。年齢は多分、アタシより二つか三つ上だろう。ハッとするような美形ではないけれど、彼の表情には人を惹きつける〝華〟がある。
「一〇〇〇円お預かりします。――五二八円のお返しです」
先ほどまでのぎこちなさが嘘のような素早さでレジを打ち、一之瀬は、あっという間にレシートと釣り銭を差し出してよこした。
そのギャップがおかしくて、笑ってしまいそうになるのをこらえながら、アタシは右手でお金を受け取り、左手にビニール袋を提げた。
「どうも」
軽く会釈をして、店を後にする。
「ありがとうございました」
一之瀬の明るいトーンに送られて外に出ると、アタシは再び腕時計に目をやった。二一時二七分。
大通りに向かって、アタシはゆっくり歩き出した。
しょせん、アタシと彼の関係は、その程度のものだ。
「――四七二円になります」
ろくに人の顔も見ずに言うと、一之瀬は商品をビニール袋につめ始めた。
愛想のカケラもない奴――と、最初は思った。でも、何度か会計をしてもらっているうちに、気がついた。ないのは〝愛想〟ではなく〝余裕〟なのだと。
現在の時刻、二一時二四分。
繁華街の裏通りにあるこのコンビニは、ちょっとした穴場だ。裏と言っても全く人通りがない訳ではなく、ちょっと歩けばオフィス街に出るし、近くには大きな公園もある。そこそこの立地条件だと思うのだけれど、いつ来ても空いていて、レジを待たされた試しがない。
もっとも、アタシが行く時間帯だけが、たまたまそうなのかもしれないけど、おかげで周囲を気にせず立ち読みができるし、長時間コピー機を占領しても誰に迷惑をかけることもない。
アタシは千円札を無言でカウンターに置き、一之瀬の手元を見つめた。
若い男性の割には、繊細で美しい指をしている。一本一本が長くて、ちょっとした動作も綺麗だ。
でも、とろい。
紙パックのミルクティー、カレーパン、ミニサイズのグリーンサラダとシュークリーム。たったこれだけのアイテムをつめるのに、ゆうに三〇秒はかかる。
スピードが勝負のコンビニエンスストアである。気の短い客なら、早くしろ、と文句の一つも言うだろう。
アタシの見る限り、一之瀬はバーコードを通し終えた商品を〝袋につめる〟という作業だけが、不得意のようだった。
重いもの、軽いもの、柔らかくつぶれやすいもの、はたまた、冷たいもの、温かいもの。数々の雑多な商品を、その特性を損ねることなく、いかに効率よく収納するかに頭を悩ませている。
ようやく商品を入れ終えた一之瀬が、ほっとしたように顔を上げた。
卵型の優しい輪郭に、二重の大きな瞳。男らしいシャープな鼻筋と、ふっくらと立体的な唇。年齢は多分、アタシより二つか三つ上だろう。ハッとするような美形ではないけれど、彼の表情には人を惹きつける〝華〟がある。
「一〇〇〇円お預かりします。――五二八円のお返しです」
先ほどまでのぎこちなさが嘘のような素早さでレジを打ち、一之瀬は、あっという間にレシートと釣り銭を差し出してよこした。
そのギャップがおかしくて、笑ってしまいそうになるのをこらえながら、アタシは右手でお金を受け取り、左手にビニール袋を提げた。
「どうも」
軽く会釈をして、店を後にする。
「ありがとうございました」
一之瀬の明るいトーンに送られて外に出ると、アタシは再び腕時計に目をやった。二一時二七分。
大通りに向かって、アタシはゆっくり歩き出した。
*
アタシがあのコンビニを利用するようになったのは、今から二ヶ月前。ここからほど近い場所にある予備校の、夏期講習に通い始めてからのことだ。
まだ二年生だから予備校なんて早い、というアタシの主張はあっさり却下され、夏休みが終わり、秋も深まりつつある今も、引き続き週一回の講習を受けさせられている。
授業は二一時ちょうどに終わり、アタシは二一時三六分のバスで帰宅する。
それまでの待ち時間をどこでつぶそうかと考えた時に、目に留まったのがあのコンビニだった。周りの店はすでにシャッターが下りていて、まるでこの店だけが昼の世界に取り残されたように浮いて見えたのを覚えている。
でも、アタシが初めて買物をした時、レジを担当してくれたのが一之瀬だったかどうかは、覚えていない。失礼な話ではあるが、コンビニの店員の顔や名前を一々把握している客なんて、めったにいないと思う。
アタシだって、一之瀬が毎回あんなにモタモタしていなければ、彼の顔や胸のネームプレートをじっくり観察することもなかっただろう。
ふいに、一之瀬の滑稽なほど真剣な表情を思い出し、アタシは微笑した。
不思議なもので、彼の顔と名前が一致した時から、ほんのわずかではあるが、彼に対する親しみのようなものが芽生えていた。
表の繁華街の賑々しさとは正反対の、うら寂しいコンビニでバイトしている青年。
彼は一体、何者なのだろう? アタシは戯れに想像してみる。
あのササクレ一つない、大事にされた指は、何か楽器を弾くからではないだろうか? ピアノとか、ギターとか。昼間は本職の音楽活動をしているけれど、駆け出しの彼は、まだまだそれ一本で食べていくことができない。だから、やむを得ず夜のコンビニでダブルワークをしている。そして、アタシが買物をした後も、ずっとレジに立ち続け、あの店で朝を迎える……。
そこまで考えて、アタシは自分の妄想力のたくましさに苦笑を浮かべた。
自慢じゃないが、アタシは割と成績が良い。学校の授業だけで十分理解できていたし、出される宿題も真面目にこなす方だから、復習も間に合っている。わざわざお金と労力をかけて予備校通いする必要性を感じない。
とは言え、不景気なこのご時勢、家計をやり繰りしてまで予備校に通わせてくれる両親の心意気には感謝している。それだけ、アタシのことを思ってくれているわけで、未来のアタシに希望をもってくれているのだから。
期待されたら、応えたいと思う。
でも、アタシは、ちょっと勉強ができるだけで、将来のビジョンが全くもって見えていない。
大きくなったら、何になりたい?
幼いころから、何度となく繰り返されてきた質問。十七歳になった今でも、アタシはマトモな答えを出せていない。
こんなアタシに、親はどんな未来を思い描いているのだろう? アタシにも見せてくれたらいいのに。
中途半端に高い学習能力より、自分にしかできない、ずば抜けて優れた一芸がほしかった。ちょうど、想像の中の一之瀬みたいに。
まだ二年生だから予備校なんて早い、というアタシの主張はあっさり却下され、夏休みが終わり、秋も深まりつつある今も、引き続き週一回の講習を受けさせられている。
授業は二一時ちょうどに終わり、アタシは二一時三六分のバスで帰宅する。
それまでの待ち時間をどこでつぶそうかと考えた時に、目に留まったのがあのコンビニだった。周りの店はすでにシャッターが下りていて、まるでこの店だけが昼の世界に取り残されたように浮いて見えたのを覚えている。
でも、アタシが初めて買物をした時、レジを担当してくれたのが一之瀬だったかどうかは、覚えていない。失礼な話ではあるが、コンビニの店員の顔や名前を一々把握している客なんて、めったにいないと思う。
アタシだって、一之瀬が毎回あんなにモタモタしていなければ、彼の顔や胸のネームプレートをじっくり観察することもなかっただろう。
ふいに、一之瀬の滑稽なほど真剣な表情を思い出し、アタシは微笑した。
不思議なもので、彼の顔と名前が一致した時から、ほんのわずかではあるが、彼に対する親しみのようなものが芽生えていた。
表の繁華街の賑々しさとは正反対の、うら寂しいコンビニでバイトしている青年。
彼は一体、何者なのだろう? アタシは戯れに想像してみる。
あのササクレ一つない、大事にされた指は、何か楽器を弾くからではないだろうか? ピアノとか、ギターとか。昼間は本職の音楽活動をしているけれど、駆け出しの彼は、まだまだそれ一本で食べていくことができない。だから、やむを得ず夜のコンビニでダブルワークをしている。そして、アタシが買物をした後も、ずっとレジに立ち続け、あの店で朝を迎える……。
そこまで考えて、アタシは自分の妄想力のたくましさに苦笑を浮かべた。
自慢じゃないが、アタシは割と成績が良い。学校の授業だけで十分理解できていたし、出される宿題も真面目にこなす方だから、復習も間に合っている。わざわざお金と労力をかけて予備校通いする必要性を感じない。
とは言え、不景気なこのご時勢、家計をやり繰りしてまで予備校に通わせてくれる両親の心意気には感謝している。それだけ、アタシのことを思ってくれているわけで、未来のアタシに希望をもってくれているのだから。
期待されたら、応えたいと思う。
でも、アタシは、ちょっと勉強ができるだけで、将来のビジョンが全くもって見えていない。
大きくなったら、何になりたい?
幼いころから、何度となく繰り返されてきた質問。十七歳になった今でも、アタシはマトモな答えを出せていない。
こんなアタシに、親はどんな未来を思い描いているのだろう? アタシにも見せてくれたらいいのに。
中途半端に高い学習能力より、自分にしかできない、ずば抜けて優れた一芸がほしかった。ちょうど、想像の中の一之瀬みたいに。
*
バスは、運行が遅れているようだった。二一時四一分を過ぎても、まだ来る気配がない。
いつものことだが、バス停に並んでいるのはアタシ一人だった。はす向かいのカーブミラーに、小さくアタシの姿が映っている。
濃紺のスキニージーンズに、ピーコックグリーンの七分丈のチュニック。軽くレイヤーの入ったショートボブの黒髪が、夜風を受けて微かに揺れている。
高校と予備校の方角が違うこともあって、アタシは一度自宅に戻り、私服に着替えてから出直すようにしている。
制服のデザインがダサいとか、そういう問題ではない。制服を着ていると、自分が何者であるかを否応なしに宣伝することになるからだ。
アタシは一応、名門と呼ばれている進学校に通っているけれど、学年トップの秀才でも、絵に描いたような優等生でもない。それなのに、この学校の制服を着ているというだけで、イメージが一人歩きしてしまう。それが、たまらなく鬱陶しい。
人を見た目で判断してはいけないと、大人は言う。でも、アタシの制服姿を見て、あれこれ言うのは決まって大人たちだ。世の中は、矛盾に満ちている。
アタシはもう一度、カーブミラーの中の自分と向き合った。制服を着ていない自分は、他人の目に、歳相応に映るのだろうか?
アタシは左手に提げていたビニール袋を、右手に持ち替えた。大して重くもないのに、指に、赤く持ち手の痕が残っている。
アタシは毎週水曜日、同じ時間にあの店に立ち寄っているけれど、その時に一之瀬が必ずいるとは限らなかった。いる時もあれば、いない時もある。
だけど、アタシはそのシフトに規則性を見出す努力はしない。別に、一之瀬に会いたくて通っているわけではないから。
ただ、いつか何かの拍子に、彼と世間話をする機会があったとしたら、聞いてみたいことがある。週一回、必ず現れるようになったアタシの存在に、彼が気づいていたかどうか。そして、その目に映るアタシは、何者に見えているのか。
アタシは、トートバッグから携帯を取り出した。ディスプレイに表示されている時刻は、二一時四六分。もう、一〇分の遅れだ。
「早く来てよ」
溜め息まじりに呟いた時、向かい側の道路をアタシと同じ高校の制服を着た男子が通り過ぎていった。シアンブルーとチャコールグレイのチェックのパンツに、白い半そでの開襟シャツ。ダークブラウンのバックパックを左肩に掛けた横顔が、何の気なしに目に入る。
「あっ」
思わず声が出た。
一之瀬だ。
いつも、コンビニのサーモンピンクの制服姿しか見たことがないので違和感はあるが、ちょっと猫背な歩き方は、店内をうろついている時の彼と一致する。
高校生だったんだ……。
アタシは、その事実に酷く落胆している自分を感じた。勝手にできあがっていた一之瀬像が、一瞬にして消えてしまった。
もちろん、売れないミュージシャンだなんて、本気で思っていたわけじゃない。でも、まさか、こんな時間にバイトをしていたのが高校生だとは、夢にも思わなかった。しかも、同じ学校だなんて、冗談じゃない。
アタシは、なぜだか無性に腹立たしくなった。
授業で疲れた後、あのコンビニで過ごす数分間の息ぬきも、今まで一之瀬を微笑ましく見守っていた気分も、急速に色あせた。
どうして、これほどまでにいら立つのか?
こみ上げてくる理不尽な怒りは、十五分後、ようやく到着したバスに乗ってからも、一向におさまらなかった。
いつものことだが、バス停に並んでいるのはアタシ一人だった。はす向かいのカーブミラーに、小さくアタシの姿が映っている。
濃紺のスキニージーンズに、ピーコックグリーンの七分丈のチュニック。軽くレイヤーの入ったショートボブの黒髪が、夜風を受けて微かに揺れている。
高校と予備校の方角が違うこともあって、アタシは一度自宅に戻り、私服に着替えてから出直すようにしている。
制服のデザインがダサいとか、そういう問題ではない。制服を着ていると、自分が何者であるかを否応なしに宣伝することになるからだ。
アタシは一応、名門と呼ばれている進学校に通っているけれど、学年トップの秀才でも、絵に描いたような優等生でもない。それなのに、この学校の制服を着ているというだけで、イメージが一人歩きしてしまう。それが、たまらなく鬱陶しい。
人を見た目で判断してはいけないと、大人は言う。でも、アタシの制服姿を見て、あれこれ言うのは決まって大人たちだ。世の中は、矛盾に満ちている。
アタシはもう一度、カーブミラーの中の自分と向き合った。制服を着ていない自分は、他人の目に、歳相応に映るのだろうか?
アタシは左手に提げていたビニール袋を、右手に持ち替えた。大して重くもないのに、指に、赤く持ち手の痕が残っている。
アタシは毎週水曜日、同じ時間にあの店に立ち寄っているけれど、その時に一之瀬が必ずいるとは限らなかった。いる時もあれば、いない時もある。
だけど、アタシはそのシフトに規則性を見出す努力はしない。別に、一之瀬に会いたくて通っているわけではないから。
ただ、いつか何かの拍子に、彼と世間話をする機会があったとしたら、聞いてみたいことがある。週一回、必ず現れるようになったアタシの存在に、彼が気づいていたかどうか。そして、その目に映るアタシは、何者に見えているのか。
アタシは、トートバッグから携帯を取り出した。ディスプレイに表示されている時刻は、二一時四六分。もう、一〇分の遅れだ。
「早く来てよ」
溜め息まじりに呟いた時、向かい側の道路をアタシと同じ高校の制服を着た男子が通り過ぎていった。シアンブルーとチャコールグレイのチェックのパンツに、白い半そでの開襟シャツ。ダークブラウンのバックパックを左肩に掛けた横顔が、何の気なしに目に入る。
「あっ」
思わず声が出た。
一之瀬だ。
いつも、コンビニのサーモンピンクの制服姿しか見たことがないので違和感はあるが、ちょっと猫背な歩き方は、店内をうろついている時の彼と一致する。
高校生だったんだ……。
アタシは、その事実に酷く落胆している自分を感じた。勝手にできあがっていた一之瀬像が、一瞬にして消えてしまった。
もちろん、売れないミュージシャンだなんて、本気で思っていたわけじゃない。でも、まさか、こんな時間にバイトをしていたのが高校生だとは、夢にも思わなかった。しかも、同じ学校だなんて、冗談じゃない。
アタシは、なぜだか無性に腹立たしくなった。
授業で疲れた後、あのコンビニで過ごす数分間の息ぬきも、今まで一之瀬を微笑ましく見守っていた気分も、急速に色あせた。
どうして、これほどまでにいら立つのか?
こみ上げてくる理不尽な怒りは、十五分後、ようやく到着したバスに乗ってからも、一向におさまらなかった。
- 2010.01.01 -
© 2010 Ao Kamisawa. All Rights Reserved.
- Celeste Blue Kingdom -
- Celeste Blue Kingdom -