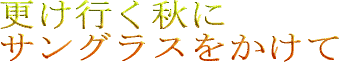Written by Ao Kamisawa.
第 2 話 遭遇 は平凡 に
人間というのは不思議なもので、一度認識してしまうと、それまで無意識でいられたものが、たちまち無視できなくなる。
否応なしに、目に飛びこんでくる。
否応なしに、目に飛びこんでくる。
*
水曜日の昼休み。
学生食堂の窓際で、クラスメイトの〝文 ちゃん〟こと、篠原文枝 ちゃんと二人、ラーメンを啜っていた時だった。
視界の端を、カレーライスのトレーを持った一之瀬が通り過ぎていった。
アタシは訳もなくギクリとして、箸を止めた。思わず、彼の行方を目で追う。
一之瀬は、少し離れた席へ、こちらに背を向けて座った。連れはいないようで、腰かけるなり、すぐにスプーンを動かし始める。
アタシは、そっと息を吐いた。
校内で一之瀬と遭遇したのは、これが初めてだった。いや、それ以前に、彼と顔を合わせること自体、あの日以来――実に二週間ぶりだった。
先週の水曜日、アタシは多少の気づまりを感じながらも、いつものように例のコンビニへ寄った。しかし、店に入った瞬間、レジに一之瀬の姿がないことに気づいた。店内をぐるりと一周して、間違いなく彼が非番であることを確信した時、アタシは安堵と共に、ほんの微かな失望を覚えた。
あの日、自分の中に湧き上がった怒りの正体について、アタシは、できるだけ客観的に分析を試みた。なぜ、彼が〝高校生〟であってはならなかったのか?
理由は、とても簡単だった。
うらやましかったのだ。
アタシと全く同じ進学校に通う身でありながら、悠々と校則違反のアルバイトに勤しめる彼が。アタシが、通いたくもない予備校でイヤイヤ授業を受けている間に、着々と己の欲しい物へと近づいている彼が。
一之瀬が何のために働いているのか、どの程度、学業と両立できているのかは知らない。でも、どんな事情にせよ、学校に通いながら働くのは、けっこう大変なことだと思う。正直、偉いと思う。アタシには、とても真似できない。
だからこそ、いら立った。
自分では頑張っているつもりなのに、目の前に、もっと頑張っている姿を見せつけられると、お前の頑張りなんて大したことないと、鼻で笑われているような気になる。お前なんて、いくら頑張っても、その程度なのだ、と。
「美央 ? どうしたの?」
気がつくと、怪訝な顔をした文ちゃんが、じっとアタシを見つめていた。
「何でもない。ちょっと、ぼんやりしてた」
アタシは笑ってごまかすと、残りのラーメンを片づけにかかった。そうでなくとも太めの麺が、のびて極太麺になっている。
「そういえば、今度の金曜日、仁美とサトちゃんからカラオケに誘われてるんだけど、美央っちも一緒に行かない?」
すでに食べ終えた文ちゃんが、両手で頬杖をつきながら言った。
テニス部の文ちゃんは、小麦色の肌に、若々しくふっくらした頬をしている。身長はアタシより一〇センチは低いが、とってもパワフルで、燃費の良い軽自動車並みにフットワークが軽い。手芸部員とは名ばかりの万年幽霊部員のアタシとは正反対で、毎日、元気にラケットを振り回している。
「ごめん。行きたいのは山々なんだけど、今月ピンチ」
「マジで? カラオケ一時間も行けないくらい?」
「うん。土曜日に映画みに行こうと思ってさ、前売り券買ったばっかりなんだ」
今週末に封切られるサイコサスペンスの洋画を、アタシはずっと楽しみにしていた。女の友情も大事にしたいと思うけど、タイミングが悪かったとしか言いようがない。
「そっかぁ。じゃあ、仕方ないか」
「ごめんね。また今度、誘ってよ」
心底残念そうに唇をとがらせている文ちゃんに、アタシは拝むように両手を合わせた。
こういう時、自分でお金を稼げたら、どんなにいいだろうと思う。
「あーあ、バイトしたいな」
ポツリと呟くと、文ちゃんが目を丸くした。
「何いってんの! バイトなんかしたら、停学になっちゃうよ?」
「わかってる。ちょっと、言ってみただけ」
アタシは小さく肩をすくめた。
どこかの誰かさんみたいに、無謀な勇気は持ち合わせていないから――と、心の中でつけ足して、アタシは一之瀬の背中を見た。広い肩と、襟足の長い真っ直ぐな黒髪。
ウチの学校は、学生の領分は学業であるという、王道すぎるほど王道な大義名分のもと、アルバイトを一切禁じている。破った場合、二週間の停学を食らう。
アタシが彼をうらやましく思うのは、そういうペナルティーを覚悟した上でバイトをすると決めた、彼の〝判断〟に対してかもしれない。
小心者のアタシは、例え下らないと思う校則でも、罰せられるのは嫌だから、素直に守ってしまう。学校側と闘ってまで改正しようという、ガッツもない。校則を破る人間を英雄視するつもりはないけれど、アタシは、本当にちっぽけだ。
その内、食事を終えた一之瀬が、ガタンと音をたてて立ち上がった。空のトレーを片手で持って、アタシたちの横の通路を、こちらに向かって歩いてくる。一歩、二歩……。
その上履きの赤いラインで、彼が三年生であることがわかった。ウチの学校は、学年ごとに上履きのラインの色が違うのだ。
すれ違う間際、アタシは一之瀬と目が合わないよう、さり気なくうつむいた。でも、本当は、そんな配慮が不要であることを、アタシは知っている。
彼はアタシに気づかない。アタシをアタシであると認識していないから。
案の定、一之瀬は、こちらを一瞥することも、振り返ることもなく、真っ直ぐに食堂から出て行った。日常ってやつは、そんなにドラマティックにはできていないのだ。
「そろそろ行こうか」
飲み切れなかったスープを残したまま、アタシはプラスチックの丼を片づけた。
学生食堂の窓際で、クラスメイトの〝
視界の端を、カレーライスのトレーを持った一之瀬が通り過ぎていった。
アタシは訳もなくギクリとして、箸を止めた。思わず、彼の行方を目で追う。
一之瀬は、少し離れた席へ、こちらに背を向けて座った。連れはいないようで、腰かけるなり、すぐにスプーンを動かし始める。
アタシは、そっと息を吐いた。
校内で一之瀬と遭遇したのは、これが初めてだった。いや、それ以前に、彼と顔を合わせること自体、あの日以来――実に二週間ぶりだった。
先週の水曜日、アタシは多少の気づまりを感じながらも、いつものように例のコンビニへ寄った。しかし、店に入った瞬間、レジに一之瀬の姿がないことに気づいた。店内をぐるりと一周して、間違いなく彼が非番であることを確信した時、アタシは安堵と共に、ほんの微かな失望を覚えた。
あの日、自分の中に湧き上がった怒りの正体について、アタシは、できるだけ客観的に分析を試みた。なぜ、彼が〝高校生〟であってはならなかったのか?
理由は、とても簡単だった。
うらやましかったのだ。
アタシと全く同じ進学校に通う身でありながら、悠々と校則違反のアルバイトに勤しめる彼が。アタシが、通いたくもない予備校でイヤイヤ授業を受けている間に、着々と己の欲しい物へと近づいている彼が。
一之瀬が何のために働いているのか、どの程度、学業と両立できているのかは知らない。でも、どんな事情にせよ、学校に通いながら働くのは、けっこう大変なことだと思う。正直、偉いと思う。アタシには、とても真似できない。
だからこそ、いら立った。
自分では頑張っているつもりなのに、目の前に、もっと頑張っている姿を見せつけられると、お前の頑張りなんて大したことないと、鼻で笑われているような気になる。お前なんて、いくら頑張っても、その程度なのだ、と。
「
気がつくと、怪訝な顔をした文ちゃんが、じっとアタシを見つめていた。
「何でもない。ちょっと、ぼんやりしてた」
アタシは笑ってごまかすと、残りのラーメンを片づけにかかった。そうでなくとも太めの麺が、のびて極太麺になっている。
「そういえば、今度の金曜日、仁美とサトちゃんからカラオケに誘われてるんだけど、美央っちも一緒に行かない?」
すでに食べ終えた文ちゃんが、両手で頬杖をつきながら言った。
テニス部の文ちゃんは、小麦色の肌に、若々しくふっくらした頬をしている。身長はアタシより一〇センチは低いが、とってもパワフルで、燃費の良い軽自動車並みにフットワークが軽い。手芸部員とは名ばかりの万年幽霊部員のアタシとは正反対で、毎日、元気にラケットを振り回している。
「ごめん。行きたいのは山々なんだけど、今月ピンチ」
「マジで? カラオケ一時間も行けないくらい?」
「うん。土曜日に映画みに行こうと思ってさ、前売り券買ったばっかりなんだ」
今週末に封切られるサイコサスペンスの洋画を、アタシはずっと楽しみにしていた。女の友情も大事にしたいと思うけど、タイミングが悪かったとしか言いようがない。
「そっかぁ。じゃあ、仕方ないか」
「ごめんね。また今度、誘ってよ」
心底残念そうに唇をとがらせている文ちゃんに、アタシは拝むように両手を合わせた。
こういう時、自分でお金を稼げたら、どんなにいいだろうと思う。
「あーあ、バイトしたいな」
ポツリと呟くと、文ちゃんが目を丸くした。
「何いってんの! バイトなんかしたら、停学になっちゃうよ?」
「わかってる。ちょっと、言ってみただけ」
アタシは小さく肩をすくめた。
どこかの誰かさんみたいに、無謀な勇気は持ち合わせていないから――と、心の中でつけ足して、アタシは一之瀬の背中を見た。広い肩と、襟足の長い真っ直ぐな黒髪。
ウチの学校は、学生の領分は学業であるという、王道すぎるほど王道な大義名分のもと、アルバイトを一切禁じている。破った場合、二週間の停学を食らう。
アタシが彼をうらやましく思うのは、そういうペナルティーを覚悟した上でバイトをすると決めた、彼の〝判断〟に対してかもしれない。
小心者のアタシは、例え下らないと思う校則でも、罰せられるのは嫌だから、素直に守ってしまう。学校側と闘ってまで改正しようという、ガッツもない。校則を破る人間を英雄視するつもりはないけれど、アタシは、本当にちっぽけだ。
その内、食事を終えた一之瀬が、ガタンと音をたてて立ち上がった。空のトレーを片手で持って、アタシたちの横の通路を、こちらに向かって歩いてくる。一歩、二歩……。
その上履きの赤いラインで、彼が三年生であることがわかった。ウチの学校は、学年ごとに上履きのラインの色が違うのだ。
すれ違う間際、アタシは一之瀬と目が合わないよう、さり気なくうつむいた。でも、本当は、そんな配慮が不要であることを、アタシは知っている。
彼はアタシに気づかない。アタシをアタシであると認識していないから。
案の定、一之瀬は、こちらを一瞥することも、振り返ることもなく、真っ直ぐに食堂から出て行った。日常ってやつは、そんなにドラマティックにはできていないのだ。
「そろそろ行こうか」
飲み切れなかったスープを残したまま、アタシはプラスチックの丼を片づけた。
- 2010.01.01 -
© 2010 Ao Kamisawa. All Rights Reserved.
- Celeste Blue Kingdom -
- Celeste Blue Kingdom -