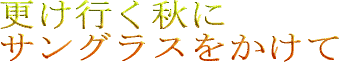Written by Ao Kamisawa.
第 3 話 熱伝導
「今日の授業は、ここまでにします」
大学院生のアルバイト講師は、いつも二一時きっかりに授業を終わらせる。どんなに切りが悪くとも、一分たりとも延長しない。
アタシは、教科書とノートを一緒くたにしてトートバッグに放り込むと、制服姿の他校生たちに混じって表に出た。
「寒っ」
思いがけず冷たい夜風が、大きく開いたスクエアネックの首筋を撫でていく。九月も末、そろそろ秋冬物を出さなければならない。
そうだ。バスを待つ間、あったかいミルクティーでも飲もう。
その思いつきが、何だか、とても良いアイディアに思えて、アタシは意気揚々とコンビニに向かった。
大学院生のアルバイト講師は、いつも二一時きっかりに授業を終わらせる。どんなに切りが悪くとも、一分たりとも延長しない。
アタシは、教科書とノートを一緒くたにしてトートバッグに放り込むと、制服姿の他校生たちに混じって表に出た。
「寒っ」
思いがけず冷たい夜風が、大きく開いたスクエアネックの首筋を撫でていく。九月も末、そろそろ秋冬物を出さなければならない。
そうだ。バスを待つ間、あったかいミルクティーでも飲もう。
その思いつきが、何だか、とても良いアイディアに思えて、アタシは意気揚々とコンビニに向かった。
*
「いらっしゃいませ」
入ってすぐの棚の前で屈みこみ、商品を補充していた一之瀬が、栄養ドリンク片手に顔を上げた。
それと同時に、思いきり目が合ってしまい、アタシは慌てて顔を背けた。嫌な客だと思われたかもしれない。
一日に二回も一之瀬に会うなんて、妙な気分だった。今まで、別世界の住人だと思っていた彼が、急に身近な存在になりすぎて、調子が狂う。
アタシは、どっと疲れを覚えた。
そうでなくとも、予備校で三時間、みっちり数学の公式をつめこまれたばかりなのだ。頭のキャパは、もう、いっぱいいっぱいだ。
こんな時は、甘い物に限る。脳を使う時に必要な栄養素はブドウ糖だというけれど、全くその通りだと思う。頭を使った後、アタシは無性に甘い物が欲しくなる。
アタシはデザートが置いてある棚をのぞいた。オーソドックスな苺のショートケーキに杏仁豆腐、白玉あんみつ……。どれも美味しそうで、中々一つにしぼれない。
散々悩んだあげく、アタシは何の変哲もないシュークリームに手を伸ばした。
いつも迷った末に辿り着くのは、一番の好物だった。たまには違う物を選んでみようと思うのだけど、気がつけば同じ物で落ち着いている。保守的なのだ。
それから、温かいペットボトル飲料のコーナーで、予定通りミルクティーを手に取った。だが、思ったほど熱くない。
もっと、熱々のが欲しかったんだけどな。
ちょっぴり不服に思いつつも、アタシは無人のレジへ向かった。
カウンターに商品を載せると、人の――アタシの気配を感じて、すぐさま一之瀬がレジに入った。
「お待たせしました」
言うが早いか、あっという間にバーコードをスキャナに通す。そして、商品を袋に入れようと、ペットボトルをつかんだ瞬間、ふっと顔を上げた。
いつものように、うつむいて作業に没頭している一之瀬の様子を眺めていたアタシは、急に顔を上げた彼と、またしても目が合ってしまった。
見ていたのが、バレたかもしれない。心拍数と体温が急上昇したのが、自分でもわかる。
「あの、ちょっとだけ、お時間いただいてもよろしいですか?」
「は?」
思いがけない言葉をかけられ、アタシは間のぬけた返事をした。
「申し訳ないんですが、これ、さっき補充したばっかりで、あんまり温まってないんです。奥に、もっと熱いのがあるはずなんで、お取り替えいたします」
一之瀬はアタシの了解を得ぬまま、ぬるいペットボトルを引っつかみ、大股でホットドリンクのコーナーへ向かった。そして、手前にあるボトルを二、三本取り出すと、空いたスペースに腕を突っこみ、一番奥にあった商品を引っぱりだした。それから、先に出したボトルを速やかに元通りにし、あっという間に戻ってくる。
あっ気にとられていたアタシは、つい、お礼を言いそびれてしまった。
一之瀬が、こんなにも細やかな心配りをする人だなんて、思いもしなかった。当たり前のことをしただけ、と言わんばかりの、押しつけがましさのない態度も好ましい。
アタシは素直に嬉しくなった。ささやかでも、心に響く優しさ。
「お待たせして、申し訳ありませんでした。二九〇円になります」
そう言って、一之瀬は苦手な袋づめに入りかけた。しかし、その手が宙に止まる。今日は、温かいものと冷たいものの組み合わせなので、袋を分けるべきかどうか逡巡したのが、傍目にもわかった。
「あの、ペットボトルの方は、シールだけ貼ってもらえればいいです。せっかく熱いのと交換してもらったし、冷めないうちに飲んじゃうんで」
アタシは、わざと一之瀬の方を見ないで言った。小銭入れを指でかき混ぜ、百円玉を出すのに懸命なフリをする。さり気ない優しさのお返しは、苦手なのだ。
「ありがとうございます」
財布に目を落としたままでも、一之瀬が微笑んだのがわかった。シュークリームだけを小さなビニール袋に入れ、ペットボトルには店のロゴがプリントされたサーモンピンクのテープをぺたりと貼る。
「三〇〇円お預かりしましたので、一〇円のお返しです」
レシートの上にちんまりと十円玉を載せ、一之瀬が差し出した。
それを、いつものように右手で受け取り、左手でシュークリームの入ったビニール袋と、むき出しのペットボトルをつまみ上げ――ようとしたところで、うまくつかめずゴロンと倒してしまった。こんな時に限って、アタシはヘマをやらかす。
慌ててつかみなおそうとしたところを、一之瀬がひょいと取り上げた。
「どうぞ」
アタシの顔を真っ直ぐに見て言う。
「熱いので、お気をつけて」
「すみません」
受け取ったボトルを胸に抱き、アタシはそそくさと扉を押した。一瞬でも早く、この場から消え去りたい気持ちでいっぱいだった。
しかし、銀色の取っ手を離す瞬間、いつもの癖で、ちらりと後方に目をやってしまう。
すると――。
「ありがとうございました。また、お越しください」
一之瀬の笑顔が、アタシを見送っていた。濡れ羽色の力強い瞳に直視され、息がつまりそうになる。
アタシは彼に笑みを返す余裕などなく、隠れるように闇にまぎれた。
その時、押し抱いたペットボトルの温もりが、じんわりと全身に広がっていくのを確かに感じた。
入ってすぐの棚の前で屈みこみ、商品を補充していた一之瀬が、栄養ドリンク片手に顔を上げた。
それと同時に、思いきり目が合ってしまい、アタシは慌てて顔を背けた。嫌な客だと思われたかもしれない。
一日に二回も一之瀬に会うなんて、妙な気分だった。今まで、別世界の住人だと思っていた彼が、急に身近な存在になりすぎて、調子が狂う。
アタシは、どっと疲れを覚えた。
そうでなくとも、予備校で三時間、みっちり数学の公式をつめこまれたばかりなのだ。頭のキャパは、もう、いっぱいいっぱいだ。
こんな時は、甘い物に限る。脳を使う時に必要な栄養素はブドウ糖だというけれど、全くその通りだと思う。頭を使った後、アタシは無性に甘い物が欲しくなる。
アタシはデザートが置いてある棚をのぞいた。オーソドックスな苺のショートケーキに杏仁豆腐、白玉あんみつ……。どれも美味しそうで、中々一つにしぼれない。
散々悩んだあげく、アタシは何の変哲もないシュークリームに手を伸ばした。
いつも迷った末に辿り着くのは、一番の好物だった。たまには違う物を選んでみようと思うのだけど、気がつけば同じ物で落ち着いている。保守的なのだ。
それから、温かいペットボトル飲料のコーナーで、予定通りミルクティーを手に取った。だが、思ったほど熱くない。
もっと、熱々のが欲しかったんだけどな。
ちょっぴり不服に思いつつも、アタシは無人のレジへ向かった。
カウンターに商品を載せると、人の――アタシの気配を感じて、すぐさま一之瀬がレジに入った。
「お待たせしました」
言うが早いか、あっという間にバーコードをスキャナに通す。そして、商品を袋に入れようと、ペットボトルをつかんだ瞬間、ふっと顔を上げた。
いつものように、うつむいて作業に没頭している一之瀬の様子を眺めていたアタシは、急に顔を上げた彼と、またしても目が合ってしまった。
見ていたのが、バレたかもしれない。心拍数と体温が急上昇したのが、自分でもわかる。
「あの、ちょっとだけ、お時間いただいてもよろしいですか?」
「は?」
思いがけない言葉をかけられ、アタシは間のぬけた返事をした。
「申し訳ないんですが、これ、さっき補充したばっかりで、あんまり温まってないんです。奥に、もっと熱いのがあるはずなんで、お取り替えいたします」
一之瀬はアタシの了解を得ぬまま、ぬるいペットボトルを引っつかみ、大股でホットドリンクのコーナーへ向かった。そして、手前にあるボトルを二、三本取り出すと、空いたスペースに腕を突っこみ、一番奥にあった商品を引っぱりだした。それから、先に出したボトルを速やかに元通りにし、あっという間に戻ってくる。
あっ気にとられていたアタシは、つい、お礼を言いそびれてしまった。
一之瀬が、こんなにも細やかな心配りをする人だなんて、思いもしなかった。当たり前のことをしただけ、と言わんばかりの、押しつけがましさのない態度も好ましい。
アタシは素直に嬉しくなった。ささやかでも、心に響く優しさ。
「お待たせして、申し訳ありませんでした。二九〇円になります」
そう言って、一之瀬は苦手な袋づめに入りかけた。しかし、その手が宙に止まる。今日は、温かいものと冷たいものの組み合わせなので、袋を分けるべきかどうか逡巡したのが、傍目にもわかった。
「あの、ペットボトルの方は、シールだけ貼ってもらえればいいです。せっかく熱いのと交換してもらったし、冷めないうちに飲んじゃうんで」
アタシは、わざと一之瀬の方を見ないで言った。小銭入れを指でかき混ぜ、百円玉を出すのに懸命なフリをする。さり気ない優しさのお返しは、苦手なのだ。
「ありがとうございます」
財布に目を落としたままでも、一之瀬が微笑んだのがわかった。シュークリームだけを小さなビニール袋に入れ、ペットボトルには店のロゴがプリントされたサーモンピンクのテープをぺたりと貼る。
「三〇〇円お預かりしましたので、一〇円のお返しです」
レシートの上にちんまりと十円玉を載せ、一之瀬が差し出した。
それを、いつものように右手で受け取り、左手でシュークリームの入ったビニール袋と、むき出しのペットボトルをつまみ上げ――ようとしたところで、うまくつかめずゴロンと倒してしまった。こんな時に限って、アタシはヘマをやらかす。
慌ててつかみなおそうとしたところを、一之瀬がひょいと取り上げた。
「どうぞ」
アタシの顔を真っ直ぐに見て言う。
「熱いので、お気をつけて」
「すみません」
受け取ったボトルを胸に抱き、アタシはそそくさと扉を押した。一瞬でも早く、この場から消え去りたい気持ちでいっぱいだった。
しかし、銀色の取っ手を離す瞬間、いつもの癖で、ちらりと後方に目をやってしまう。
すると――。
「ありがとうございました。また、お越しください」
一之瀬の笑顔が、アタシを見送っていた。濡れ羽色の力強い瞳に直視され、息がつまりそうになる。
アタシは彼に笑みを返す余裕などなく、隠れるように闇にまぎれた。
その時、押し抱いたペットボトルの温もりが、じんわりと全身に広がっていくのを確かに感じた。
- 2010.01.01 -
© 2010 Ao Kamisawa. All Rights Reserved.
- Celeste Blue Kingdom -
- Celeste Blue Kingdom -