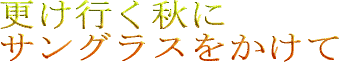Written by Ao Kamisawa.
第 4 話 木曜日 に
予備校に忘れ物をしたかもしれないことに気づいたのは、翌日――木曜日の朝だった。
やっぱり、ない。
朝一番に教室の机をのぞきこんだアタシは、低くうなった。
昨夜、宿題を片づけようと思って通学カバンをあけたら、課題のプリントをはさんでおいたファイルが入っていなかった。
恐らく、教室の机の中にでも置き忘れたのだろう。そう簡単に考えていたのが甘かった。
机の中にも、念のため調べてみたロッカーの中にも、ファイルはなかった。
他に心当たりがあるとすれば、予備校だった。通学カバンから、必要な物をトートバッグへ移し変えた際、余計なファイルを持っていったあげく、講義室に置き忘れてきた可能性がある。
アタシは昼休みまで待って、予備校に電話をかけた。すると、不幸中の幸い、忘れ物として届けられているとのこと。
事務の女性に礼を言い、今日中に取りに行く旨を伝え、アタシは電話を切った。
やっぱり、ない。
朝一番に教室の机をのぞきこんだアタシは、低くうなった。
昨夜、宿題を片づけようと思って通学カバンをあけたら、課題のプリントをはさんでおいたファイルが入っていなかった。
恐らく、教室の机の中にでも置き忘れたのだろう。そう簡単に考えていたのが甘かった。
机の中にも、念のため調べてみたロッカーの中にも、ファイルはなかった。
他に心当たりがあるとすれば、予備校だった。通学カバンから、必要な物をトートバッグへ移し変えた際、余計なファイルを持っていったあげく、講義室に置き忘れてきた可能性がある。
アタシは昼休みまで待って、予備校に電話をかけた。すると、不幸中の幸い、忘れ物として届けられているとのこと。
事務の女性に礼を言い、今日中に取りに行く旨を伝え、アタシは電話を切った。
*
放課後、いつものように自宅に戻って着替えていくべきか、迷った。事務所に顔を出して、忘れ物を受け取って帰るだけなのに、わざわざ出直すのも面倒な気がする。
だが、しばらく思案して、結局、いつも通り私服で行くことに決めた。先日、アタシが制服姿の一之瀬を目撃したように、いつ、どこで、誰に見られているかわからないから。
「あれ、美央っち、もう帰るの?」
すでに帰り支度を終えていたアタシを見て、掃除当番から戻ったばかりの文ちゃんは、意外そうな顔をした。今日、予備校の日じゃないよね? と、首をかしげる。
「昨日、忘れ物してきちゃってさ。今から取りに行くところ」
文ちゃんの言葉にうなずきながら、アタシは肩をすくめた。
用事がない日、アタシは大抵、下校時間ぎりぎりまで図書室で過ごすことにしている。普通に本を読んだり、勉強したり、ぼーっとしたり。
この習慣は高校に入学したばかりのころから続いており、去年もクラスメイトだった文ちゃんも良く知っていることだった。
「しっかり者の美央にしては珍しいね」
他意のない文ちゃんの発言に、内心ひっかかりを覚えながらも、アタシは真顔でとぼけてみせる。
「そうなの。サルも木から落ちるっていうか、弘法にも筆の誤りっていうか?」
「いや、それ、使い方間違ってるし」
文ちゃんはケタケタ笑いながらツッコムと、ラケットを小脇に抱えた。
「じゃあ、私、部活行くね」
「ん、いってらっしゃい」
テニスが好きで好きでたまらない、と言わんばかりの文ちゃんを、アタシは笑顔で見送った。
客観的見解が、必ずしも事実であるとは限らない。人から〝しっかり〟していると評されるたび、アタシは首をかしげてしまう。
将来の夢も、やりたいことも見つけられないアタシの、一体どこが〝しっかり〟しているんだろう? こんなにも不安定なのに。
アタシは小さいころから、夢のない子供だった。〝こうなりたい〟と思う以前に〝こういう風にはなれないだろう〟というブレーキが働く。
例えば、アタシは絵を描くのが好きだ。でも、それは寝食を忘れて熱中してしまう類の〝好き〟ではなかったし、画家になれるほどの腕前でもない。
スポーツだって得意だ。中学生のころはバスケ部のレギュラーだったし、今だって体育の成績は悪くない。だけど、プロを目指せるほどの能力は秘めていない。
とどのつまり、何をやっても中途半端なのだ。勉強も、芸術も、運動も。
何をやっても、それなりに楽しい。
でも、文ちゃんにとってのテニスみたいに、将来性とか進路とか、そういう現実的なハードルを全く無視して打ちこめる〝何か〟が、アタシにも欲しかった。
これがないと、生きている意味がない。
そう思えるくらい、強烈な〝何か〟が。
だが、しばらく思案して、結局、いつも通り私服で行くことに決めた。先日、アタシが制服姿の一之瀬を目撃したように、いつ、どこで、誰に見られているかわからないから。
「あれ、美央っち、もう帰るの?」
すでに帰り支度を終えていたアタシを見て、掃除当番から戻ったばかりの文ちゃんは、意外そうな顔をした。今日、予備校の日じゃないよね? と、首をかしげる。
「昨日、忘れ物してきちゃってさ。今から取りに行くところ」
文ちゃんの言葉にうなずきながら、アタシは肩をすくめた。
用事がない日、アタシは大抵、下校時間ぎりぎりまで図書室で過ごすことにしている。普通に本を読んだり、勉強したり、ぼーっとしたり。
この習慣は高校に入学したばかりのころから続いており、去年もクラスメイトだった文ちゃんも良く知っていることだった。
「しっかり者の美央にしては珍しいね」
他意のない文ちゃんの発言に、内心ひっかかりを覚えながらも、アタシは真顔でとぼけてみせる。
「そうなの。サルも木から落ちるっていうか、弘法にも筆の誤りっていうか?」
「いや、それ、使い方間違ってるし」
文ちゃんはケタケタ笑いながらツッコムと、ラケットを小脇に抱えた。
「じゃあ、私、部活行くね」
「ん、いってらっしゃい」
テニスが好きで好きでたまらない、と言わんばかりの文ちゃんを、アタシは笑顔で見送った。
客観的見解が、必ずしも事実であるとは限らない。人から〝しっかり〟していると評されるたび、アタシは首をかしげてしまう。
将来の夢も、やりたいことも見つけられないアタシの、一体どこが〝しっかり〟しているんだろう? こんなにも不安定なのに。
アタシは小さいころから、夢のない子供だった。〝こうなりたい〟と思う以前に〝こういう風にはなれないだろう〟というブレーキが働く。
例えば、アタシは絵を描くのが好きだ。でも、それは寝食を忘れて熱中してしまう類の〝好き〟ではなかったし、画家になれるほどの腕前でもない。
スポーツだって得意だ。中学生のころはバスケ部のレギュラーだったし、今だって体育の成績は悪くない。だけど、プロを目指せるほどの能力は秘めていない。
とどのつまり、何をやっても中途半端なのだ。勉強も、芸術も、運動も。
何をやっても、それなりに楽しい。
でも、文ちゃんにとってのテニスみたいに、将来性とか進路とか、そういう現実的なハードルを全く無視して打ちこめる〝何か〟が、アタシにも欲しかった。
これがないと、生きている意味がない。
そう思えるくらい、強烈な〝何か〟が。
*
「どうも、ありがとうございました」
一階にある事務所の窓口でファイルを受け取ると、アタシは職員の女性にお辞儀をして、ビルを出た。
一五時四七分。傾きはじめた太陽が、林立する雑居ビルの壁面を眩しいほどに照らしている。こんな明るい時間にこの辺りを歩くのは、初めてだった。
その時ふと、斜め向かいの通り沿いにある、あのコンビニの看板が目に入った。
いつもと違う曜日の、いつもと違う時間帯。あの店は、やはりスカスカの穴場状態なのだろうか? そして、彼は――。
しばらくためらってから、アタシは横断歩道に向かって歩き出した。
一階にある事務所の窓口でファイルを受け取ると、アタシは職員の女性にお辞儀をして、ビルを出た。
一五時四七分。傾きはじめた太陽が、林立する雑居ビルの壁面を眩しいほどに照らしている。こんな明るい時間にこの辺りを歩くのは、初めてだった。
その時ふと、斜め向かいの通り沿いにある、あのコンビニの看板が目に入った。
いつもと違う曜日の、いつもと違う時間帯。あの店は、やはりスカスカの穴場状態なのだろうか? そして、彼は――。
しばらくためらってから、アタシは横断歩道に向かって歩き出した。
*
ちょっと時間が違うだけで、こんなにも変わるものかとビックリするほど、夕方のコンビニは盛況だった。雑誌コーナーには人が群がり、レジはタバコを注文するビジネスマンで、ちょっとした行列ができている。
そこに一之瀬の姿はなく、アタシは他人事ながらほっとした。よけいなお世話だが、彼の処理スピードでは、これだけの客をさばき切れないかもしれないと思った。もっとも、レジを〝打つ〟作業だけなら、他のスタッフに一歩も引けを取らないけれど。
そんなことを考えながら、アタシは店内を一回りしてみた。一之瀬はおろか、棚卸しや商品を補充している店員の姿も見えない。
けっこう混んでるし、そろそろ出よう。
アタシは出口に行きかけたが、その前に、帰りのバス時間だけ確認しておこうと思い直した。バス停の周りには、昼間でも時間をつぶせるようなスポットがないのだ。
邪魔にならないよう、店の奥の隅っこで時刻表をひろげ、アタシは時間軸を指でなぞった。次のバスが来るまで、あと七分。
それぐらいなら、バス停の前で待ってよう。
そう思って、時刻表をしまい終えた時だった。
すぐ傍のバックヤードの扉が開いて、私服姿の男性が出てきた。ストレートのブラックジーンズに、ネイビーブルーのボタンシャツ。歩きながら襟の乱れを整えている指の美しさは、まごうかたなき一之瀬だった。
アタシは、思わず立ちすくんだ。フロアに見当たらなかったので、てっきり非番なのだと思いこんでいた。
一之瀬の方はというと、アタシには目もくれず、混みあっているレジの前を、軽く会釈して通り過ぎた。そして、そのまま出口へと歩いていく。
どこ行くんだろう? やっぱり、非番?
アタシは腕時計に目をやった。次のバスが来るまで、あと五分。これを逃すと、三〇分後まで待たねばならない。
でも――。
一之瀬から少し遅れて、アタシも店を出た。
どんどん遠ざかっていく彼と、バス停のある方向を一瞬見比べ、歩き出す。
好奇心の赴くまま、一之瀬の後を追って。
そこに一之瀬の姿はなく、アタシは他人事ながらほっとした。よけいなお世話だが、彼の処理スピードでは、これだけの客をさばき切れないかもしれないと思った。もっとも、レジを〝打つ〟作業だけなら、他のスタッフに一歩も引けを取らないけれど。
そんなことを考えながら、アタシは店内を一回りしてみた。一之瀬はおろか、棚卸しや商品を補充している店員の姿も見えない。
けっこう混んでるし、そろそろ出よう。
アタシは出口に行きかけたが、その前に、帰りのバス時間だけ確認しておこうと思い直した。バス停の周りには、昼間でも時間をつぶせるようなスポットがないのだ。
邪魔にならないよう、店の奥の隅っこで時刻表をひろげ、アタシは時間軸を指でなぞった。次のバスが来るまで、あと七分。
それぐらいなら、バス停の前で待ってよう。
そう思って、時刻表をしまい終えた時だった。
すぐ傍のバックヤードの扉が開いて、私服姿の男性が出てきた。ストレートのブラックジーンズに、ネイビーブルーのボタンシャツ。歩きながら襟の乱れを整えている指の美しさは、まごうかたなき一之瀬だった。
アタシは、思わず立ちすくんだ。フロアに見当たらなかったので、てっきり非番なのだと思いこんでいた。
一之瀬の方はというと、アタシには目もくれず、混みあっているレジの前を、軽く会釈して通り過ぎた。そして、そのまま出口へと歩いていく。
どこ行くんだろう? やっぱり、非番?
アタシは腕時計に目をやった。次のバスが来るまで、あと五分。これを逃すと、三〇分後まで待たねばならない。
でも――。
一之瀬から少し遅れて、アタシも店を出た。
どんどん遠ざかっていく彼と、バス停のある方向を一瞬見比べ、歩き出す。
好奇心の赴くまま、一之瀬の後を追って。
- 2010.01.01 -
© 2010 Ao Kamisawa. All Rights Reserved.
- Celeste Blue Kingdom -
- Celeste Blue Kingdom -