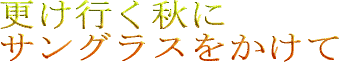Written by Ao Kamisawa.
第 5 話 放課後 の魔術師
人生初のストーキングは、たったの三分で終了した。
着いた先は近くの公園で、アタシは思わず安堵した。うっかり彼の家まで突き止めちゃったりせずにすんで、本当に良かった。
それにしても、こんなところに何の用事だろう?
オフィス街と繁華街の境界にあたるこの公園は、春には桜の名所となる、緑豊かな憩いの場だ。ジャングルジムやブランコなどの遊具のほかに、しょぼいが人工の池もある。
土日には、広場を利用したフリーマーケットやイベントも開かれているらしいが、今日は平日。小学校低学年の男の子が数人、鬼ごっこをしているだけだった。
アタシは目立たないように、一之瀬から数メーター離れたベンチに腰を下ろし、携帯を取り出した。メールでも打っているフリをしながら、彼の様子をうかがう。……何だか、本当にストーカーになった気分だ。
そんなアタシの葛藤など知る由もない一之瀬は、鉄棒の傍らにあるベンチにバックパックを下ろした。そして、中から、おもむろに黒い布を取り出し――。
何を始める気?
アタシは思わず携帯から顔を上げ、しげしげと眺めてしまった。彼が何をしたいのか、全くわからない。
一之瀬が取り出した布は意外と大きくて、シーツくらいのサイズだった。それをバサリと鉄棒にかけ、両サイドを洗濯ばさみで留める。ちょうど布団干しでもするみたいに。
そこへ、さっきまで鬼ごっこをしていた小学生たちが、吸い寄せられるように駆けて来た。まるで、一之瀬の到着を待ち侘びていたかのようだ。
「遅かったね」
「ねぇねぇ、何だすの?」
「手伝ってあげようか?」
ベンチの前でしゃがんで、バックパックを探っている一之瀬の背に向かって、男の子たちが口々に話しかけた。その声の調子にも、表情にも、まるで警戒心がない。やはり、顔なじみだったのだ。
高校生と小学生。一見して、何の接点も見出せない組み合わせである。
「大丈夫」
男の子の申し出を笑顔で辞退しながら、一之瀬は立ち上がった。
「今日は、これしか使わないから」
そう言って子供たちに何かを見せているが、掌にすっぽりと納まっていて、ここからは全く見えない。だが――。
「えー、ただの安全ピン?」
「つまんなーい!」
子供たちが一斉にブーイングを上げた。
黒いシーツと安全ピン。状況は把握できたが、目的がますますわからなくなる。
「あのさぁ、見る前から『つまんなーい』とか言わないでくれる?」
からかうように子供の口調を真似ると、一之瀬は鉄棒の――シーツの前に立った。すっと背筋を伸ばし、右手を胸の前まで持ち上げた刹那、彼の指先――安全ピンがキラリと夕陽をはじいた。
その、舞でも始めるような優美な手つきに、アタシは、たちまち目を奪われた。衆目を惹きつけてやまない、妖しい魔術師みたい――。
この時、アタシは気づいた。
あの黒い布はステージなのだと。これから始まるのは、まさに魔術 だ。
「さて、皆さん。今、僕が持っているのは、何の変哲もない〝ただの安全ピン〟です。ほら、よく見て? 超フツーでしょう?」
そう言って、子供の一人に安全ピンを確かめさせる。
「どう? 何か、おかしなところはある?」
「ううん。普通の安全ピンだった」
「けっこう」
鷹揚にうなずいて、一之瀬は子供たちの顔をぐるりと見回した。
「では、この極々普通の安全ピン二本を、こうして一本ずつ、両手に持ちます」
再び、子供の眼前にピンをかざして見せる。
遠目に見ていても、子供たちの視線が、一之瀬の手元に釘づけになっているのがわかった。小さな観客たちは、彼の創り出した奇術の空間に、どっぷりとつかっている。
ふいに、一之瀬は微笑んだ。たったそれだけで、暗闇の中、突然スポットライトが当てられたように、存在が浮き立つ。
きっと、このタイミングでの笑顔さえもが、テクニックの一つなのだろう。観客の目が、ほんの一瞬だけ、一之瀬の顔に注がれる。
そして――。
「はい、よーく見ててくださいねー。この二つのピンを、こうやって交差させて、スーッとこすると……」
「あっ! つながった!」
「嘘ぉ! 何で?」
「すっげぇー!」
あっという間に奇術が成功し、子供たちは騒然となった。一之瀬の手から、一本につながった安全ピンを奪い取り、ためつすがめつ検分を始める。
正直なところ、子供たちがうらやましかった。クロースアップマジックは、マジシャンの手元を見ていなければ話にならない。アタシも、間近で見たかった。
子供だけでなく、もっとたくさんのギャラリーがいれば、その他大勢に混じって堂々とショーを楽しめるのに。そう思ってから、そんな風に考えてしまう、消極的な自分が情けなくなった。それに比べて、一之瀬は――。
「な? 面白かっただろ?」
興奮している子供たちを見下ろしながら、彼は満足げだった。つい先ほどまでの神秘的とも呼べる雰囲気は少しも残っていないけれど、楽しげで、誇らしげで、何より生き生きしている。
その表情を見て、いいな、と思った。こんな風に笑う一之瀬の顔は、例え、何百回、何千回、あのコンビニに通っても、絶対に見られない。
「さっ、今日はこれでおしまい。解散!」
パンッと両手を打って、一之瀬がお開きを宣言した。
「ええー、やだよ。まだ早いもん」
「さっきの、もう一回見せてよ」
子供たちは、一之瀬にすがるようにして異を唱えた。
アタシも、子供たちの気持ちと同じだった。もう一度、いや、今度こそ、最初からよく見せてほしい。
勇気を出して、お願いしてみようか?
いや、でも、いきなり声かけて、ドン引きされたら嫌だし。
そんなことになったら、もう二度と、あのコンビニにも行けない。それは困る。
でも、やっぱり見てみたい。
どうしよう、どうしよう……?
ごちゃごちゃ考えていたら、頭がくらくらしてきた。今を逃がしたら、こんなチャンスは二度とないかもしれない。
でも、でも、でも――。
「ダーメ。残念だけど、これから、すぐにバイトなんだ」
一之瀬はにっこり笑うと、にわか舞台の撤去を始めた。
アタシは、全身から力がぬけるのを感じた。タイムアップ――。
意気地なしのアタシに、ぴったりの結末だと思った。うだうだ悩んでいる間に、声をかける時間すら失ってしまうなんて。
一之瀬は、外した洗濯ばさみをジーンズのポケットに突っこむと、手早く布を畳んだ。とても、慣れた手つきだった。
アタシと同様、観念した子供たちは、ランドセルを背負いながらも、ぐずぐずとその場に居残っている。
「ねぇ、今度はいつやるの?」
子供の一人が発した問いに、アタシはドキリとするくらい反応した。
〝次〟が、あるの?
アタシは、盗み聞きしているという罪悪感すら忘れて、彼らの会話に耳を澄ませた。
「んー、そうだなぁ――」
バックパックに布を押しこみながら、一之瀬は考えるように宙を見た。
「明後日だな。土曜日。たぶん、一時か二時には……」
あいまいに呟いた後、彼は、しっかり言いなおした。
「土曜日の一時に、ここで待ってるよ」
「やったぁ!」
子供たちの歓声と、アタシが心の中でガッツポーズを出したのは同時だった。
土曜の一三時。開演時間を、しっかり頭に叩きこむ。
「絶対だよ?」
「おう。お父さんとお母さんと、美人のお姉さんも連れてきていいよ」
一之瀬はニッと唇を持ち上げ、イタズラっ子のように笑った。あんな小さな子供を相手に、よく言う。
「わかった」
「またねー」
子供たちは、ランドセルの金具をカチャカチャ言わせながら、元気に去って行った。
その後ろ姿を、最後の一人まで見送っていた一之瀬は、やがて大きく伸びをした。それから、バックパックを引ったくるように担いで、もと来た道を引き返していく。
アタシは、もう追わなかった。
彼の行く先がわかっていることに、なぜだか、とても安心する。
アタシは、足元に伸びた長い影を見下ろし、次いで、西の空を見上げた。沈みかけの太陽と思いきり目が合い、涙がにじむ。
今日、この公園にくることができて、本当に良かった。偶然、忘れ物をした自分に感謝したいくらい。
アタシはショルダーバッグを肩にかけると、勢いをつけて立ち上がった。すっかり人影の消えた公園を、足早に通りぬける。
次のバスには、何としても乗らなければならない。
着いた先は近くの公園で、アタシは思わず安堵した。うっかり彼の家まで突き止めちゃったりせずにすんで、本当に良かった。
それにしても、こんなところに何の用事だろう?
オフィス街と繁華街の境界にあたるこの公園は、春には桜の名所となる、緑豊かな憩いの場だ。ジャングルジムやブランコなどの遊具のほかに、しょぼいが人工の池もある。
土日には、広場を利用したフリーマーケットやイベントも開かれているらしいが、今日は平日。小学校低学年の男の子が数人、鬼ごっこをしているだけだった。
アタシは目立たないように、一之瀬から数メーター離れたベンチに腰を下ろし、携帯を取り出した。メールでも打っているフリをしながら、彼の様子をうかがう。……何だか、本当にストーカーになった気分だ。
そんなアタシの葛藤など知る由もない一之瀬は、鉄棒の傍らにあるベンチにバックパックを下ろした。そして、中から、おもむろに黒い布を取り出し――。
何を始める気?
アタシは思わず携帯から顔を上げ、しげしげと眺めてしまった。彼が何をしたいのか、全くわからない。
一之瀬が取り出した布は意外と大きくて、シーツくらいのサイズだった。それをバサリと鉄棒にかけ、両サイドを洗濯ばさみで留める。ちょうど布団干しでもするみたいに。
そこへ、さっきまで鬼ごっこをしていた小学生たちが、吸い寄せられるように駆けて来た。まるで、一之瀬の到着を待ち侘びていたかのようだ。
「遅かったね」
「ねぇねぇ、何だすの?」
「手伝ってあげようか?」
ベンチの前でしゃがんで、バックパックを探っている一之瀬の背に向かって、男の子たちが口々に話しかけた。その声の調子にも、表情にも、まるで警戒心がない。やはり、顔なじみだったのだ。
高校生と小学生。一見して、何の接点も見出せない組み合わせである。
「大丈夫」
男の子の申し出を笑顔で辞退しながら、一之瀬は立ち上がった。
「今日は、これしか使わないから」
そう言って子供たちに何かを見せているが、掌にすっぽりと納まっていて、ここからは全く見えない。だが――。
「えー、ただの安全ピン?」
「つまんなーい!」
子供たちが一斉にブーイングを上げた。
黒いシーツと安全ピン。状況は把握できたが、目的がますますわからなくなる。
「あのさぁ、見る前から『つまんなーい』とか言わないでくれる?」
からかうように子供の口調を真似ると、一之瀬は鉄棒の――シーツの前に立った。すっと背筋を伸ばし、右手を胸の前まで持ち上げた刹那、彼の指先――安全ピンがキラリと夕陽をはじいた。
その、舞でも始めるような優美な手つきに、アタシは、たちまち目を奪われた。衆目を惹きつけてやまない、妖しい魔術師みたい――。
この時、アタシは気づいた。
あの黒い布はステージなのだと。これから始まるのは、まさに
「さて、皆さん。今、僕が持っているのは、何の変哲もない〝ただの安全ピン〟です。ほら、よく見て? 超フツーでしょう?」
そう言って、子供の一人に安全ピンを確かめさせる。
「どう? 何か、おかしなところはある?」
「ううん。普通の安全ピンだった」
「けっこう」
鷹揚にうなずいて、一之瀬は子供たちの顔をぐるりと見回した。
「では、この極々普通の安全ピン二本を、こうして一本ずつ、両手に持ちます」
再び、子供の眼前にピンをかざして見せる。
遠目に見ていても、子供たちの視線が、一之瀬の手元に釘づけになっているのがわかった。小さな観客たちは、彼の創り出した奇術の空間に、どっぷりとつかっている。
ふいに、一之瀬は微笑んだ。たったそれだけで、暗闇の中、突然スポットライトが当てられたように、存在が浮き立つ。
きっと、このタイミングでの笑顔さえもが、テクニックの一つなのだろう。観客の目が、ほんの一瞬だけ、一之瀬の顔に注がれる。
そして――。
「はい、よーく見ててくださいねー。この二つのピンを、こうやって交差させて、スーッとこすると……」
「あっ! つながった!」
「嘘ぉ! 何で?」
「すっげぇー!」
あっという間に奇術が成功し、子供たちは騒然となった。一之瀬の手から、一本につながった安全ピンを奪い取り、ためつすがめつ検分を始める。
正直なところ、子供たちがうらやましかった。クロースアップマジックは、マジシャンの手元を見ていなければ話にならない。アタシも、間近で見たかった。
子供だけでなく、もっとたくさんのギャラリーがいれば、その他大勢に混じって堂々とショーを楽しめるのに。そう思ってから、そんな風に考えてしまう、消極的な自分が情けなくなった。それに比べて、一之瀬は――。
「な? 面白かっただろ?」
興奮している子供たちを見下ろしながら、彼は満足げだった。つい先ほどまでの神秘的とも呼べる雰囲気は少しも残っていないけれど、楽しげで、誇らしげで、何より生き生きしている。
その表情を見て、いいな、と思った。こんな風に笑う一之瀬の顔は、例え、何百回、何千回、あのコンビニに通っても、絶対に見られない。
「さっ、今日はこれでおしまい。解散!」
パンッと両手を打って、一之瀬がお開きを宣言した。
「ええー、やだよ。まだ早いもん」
「さっきの、もう一回見せてよ」
子供たちは、一之瀬にすがるようにして異を唱えた。
アタシも、子供たちの気持ちと同じだった。もう一度、いや、今度こそ、最初からよく見せてほしい。
勇気を出して、お願いしてみようか?
いや、でも、いきなり声かけて、ドン引きされたら嫌だし。
そんなことになったら、もう二度と、あのコンビニにも行けない。それは困る。
でも、やっぱり見てみたい。
どうしよう、どうしよう……?
ごちゃごちゃ考えていたら、頭がくらくらしてきた。今を逃がしたら、こんなチャンスは二度とないかもしれない。
でも、でも、でも――。
「ダーメ。残念だけど、これから、すぐにバイトなんだ」
一之瀬はにっこり笑うと、にわか舞台の撤去を始めた。
アタシは、全身から力がぬけるのを感じた。タイムアップ――。
意気地なしのアタシに、ぴったりの結末だと思った。うだうだ悩んでいる間に、声をかける時間すら失ってしまうなんて。
一之瀬は、外した洗濯ばさみをジーンズのポケットに突っこむと、手早く布を畳んだ。とても、慣れた手つきだった。
アタシと同様、観念した子供たちは、ランドセルを背負いながらも、ぐずぐずとその場に居残っている。
「ねぇ、今度はいつやるの?」
子供の一人が発した問いに、アタシはドキリとするくらい反応した。
〝次〟が、あるの?
アタシは、盗み聞きしているという罪悪感すら忘れて、彼らの会話に耳を澄ませた。
「んー、そうだなぁ――」
バックパックに布を押しこみながら、一之瀬は考えるように宙を見た。
「明後日だな。土曜日。たぶん、一時か二時には……」
あいまいに呟いた後、彼は、しっかり言いなおした。
「土曜日の一時に、ここで待ってるよ」
「やったぁ!」
子供たちの歓声と、アタシが心の中でガッツポーズを出したのは同時だった。
土曜の一三時。開演時間を、しっかり頭に叩きこむ。
「絶対だよ?」
「おう。お父さんとお母さんと、美人のお姉さんも連れてきていいよ」
一之瀬はニッと唇を持ち上げ、イタズラっ子のように笑った。あんな小さな子供を相手に、よく言う。
「わかった」
「またねー」
子供たちは、ランドセルの金具をカチャカチャ言わせながら、元気に去って行った。
その後ろ姿を、最後の一人まで見送っていた一之瀬は、やがて大きく伸びをした。それから、バックパックを引ったくるように担いで、もと来た道を引き返していく。
アタシは、もう追わなかった。
彼の行く先がわかっていることに、なぜだか、とても安心する。
アタシは、足元に伸びた長い影を見下ろし、次いで、西の空を見上げた。沈みかけの太陽と思いきり目が合い、涙がにじむ。
今日、この公園にくることができて、本当に良かった。偶然、忘れ物をした自分に感謝したいくらい。
アタシはショルダーバッグを肩にかけると、勢いをつけて立ち上がった。すっかり人影の消えた公園を、足早に通りぬける。
次のバスには、何としても乗らなければならない。
- 2010.01.01 -
© 2010 Ao Kamisawa. All Rights Reserved.
- Celeste Blue Kingdom -
- Celeste Blue Kingdom -