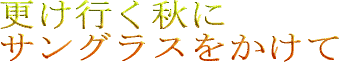Written by Ao Kamisawa.
第 6 話 レンズ越 しに祈 りを
週末をこんなにも待ち遠しく思ったのは、久しぶりだった。
「じゃあ、行ってきます」
玄関を出ると、見事な秋晴れだった。高く澄み渡った天空を、遠く鳥影が過ぎっていく。
こんな日は、それだけでラッキーな気分になれるから不思議だ。
明るい日差しを浴びながら、アタシはサングラスをかけた。薄い、オレンジブラウンのレンズが入っている。
でもそれは、眩しいからじゃない。焼け石に水的な変装のためだ。
色とデザインに一目ぼれして買ったこのサングラスは、遮光性の低い、実用には極めて不向きな一品だった。本当に必要とされる盛夏には、ほとんど用を成さない。
だけど、アタシは気に入っている。全く必要に迫られない、アタシ向きの逸品。
「じゃあ、行ってきます」
玄関を出ると、見事な秋晴れだった。高く澄み渡った天空を、遠く鳥影が過ぎっていく。
こんな日は、それだけでラッキーな気分になれるから不思議だ。
明るい日差しを浴びながら、アタシはサングラスをかけた。薄い、オレンジブラウンのレンズが入っている。
でもそれは、眩しいからじゃない。焼け石に水的な変装のためだ。
色とデザインに一目ぼれして買ったこのサングラスは、遮光性の低い、実用には極めて不向きな一品だった。本当に必要とされる盛夏には、ほとんど用を成さない。
だけど、アタシは気に入っている。全く必要に迫られない、アタシ向きの逸品。
*
いつもの停留所でバスを降り、いつもと違う道を行くのは新鮮だった。歩くルートや時間が違うだけで、街は別な表情を見せる。
公園に足を踏みいれると、アタシはにわかに緊張しはじめた。今日は土曜日だけれど、特別なイベントはないようだった。こんな日に、一人、ウロウロしている自分は何者に見られるのかと、不安になる。
でも、引き返すつもりはなかった。アタシは鉄棒のある広場へと出た。
先日と同じように、小学生くらいの男の子が数人、ドッジボールをして遊んでいる。よく見ると、この前の子供たちだった。
良かった。一人じゃない。
観客がアタシだけではなさそうなことも、今日を楽しみにしていたのが自分一人じゃなかったことも、何だか嬉しかった。
ほっとしながら鉄棒に目をやると、すでに黒い布がかけられていた。しかし、肝心のマジシャンの姿が見当たらない。
時刻は一二時五七分――開演三分前だ。
とりあえず、アタシはこの間と同じベンチに腰を下ろした。手持ちぶさたに携帯をいじる。
あ、メールだ。
マナーモードにしていて気づかなかったが、バスに乗っている間に、文ちゃんからメールがきていた。
『映画、おもしろかったかな?
昨日のカラオケ、美央っちがこれなくて 二人とも残念がってたヨ。
今度こそ、一緒に行こうね』
絵文字まじりの短い文面に目を走らせて、アタシはハッとした。
しまった! 映画!
今日から公開だったのに。あんなに前から楽しみにしていたのを、すっかり忘れてしまうなんて。
何やってんだろ、アタシ……。
今日、この後で観に行ってもよかったけれど、あいにく、チケットは家に置いてきてしまった。
『急な用事で、観に行けなかったよ。
来週のお楽しみになっちゃった。
カラオケ、アタシも行きたかったなぁ。
ホント残念! また誘ってね!』
とり急ぎ返信メールを送り、アタシは携帯をしまった。
どうして忘れたのかは、考えるまでもない。アタシは、その元凶に目を移した。
赤いビールケースを両手に二個ずつ持った一之瀬が、子供たちにとり囲まれながらやって来る。
もしかして、バイト先から借りてきたんだろうか? 何らかのマジックに必要なのだろうが、一体、何に使うと言って借りたのだろう? それとも、バイト仲間たちは知っているんだろうか? 彼がストリートマジシャンであることを。
この街の景色と同様、一之瀬にもたくさんの顔がある。学食でつまらなさそうに食事していた高校生の顔、苦手な作業も一生懸命がんばっている店員の顔。そして、子供相手でも手をぬかない、パフォーマーの顔。どれも、違う時間、違う場所で見るからこそ、出会える顔だ。
映画を公開初日に観られなかったのは残念だったけれど、後悔というほどではなかった。
この日、この場所で、たった一度しか観られないショーと重なってしまったのだから、こちらを選ばないわけにはいかない。
公園に足を踏みいれると、アタシはにわかに緊張しはじめた。今日は土曜日だけれど、特別なイベントはないようだった。こんな日に、一人、ウロウロしている自分は何者に見られるのかと、不安になる。
でも、引き返すつもりはなかった。アタシは鉄棒のある広場へと出た。
先日と同じように、小学生くらいの男の子が数人、ドッジボールをして遊んでいる。よく見ると、この前の子供たちだった。
良かった。一人じゃない。
観客がアタシだけではなさそうなことも、今日を楽しみにしていたのが自分一人じゃなかったことも、何だか嬉しかった。
ほっとしながら鉄棒に目をやると、すでに黒い布がかけられていた。しかし、肝心のマジシャンの姿が見当たらない。
時刻は一二時五七分――開演三分前だ。
とりあえず、アタシはこの間と同じベンチに腰を下ろした。手持ちぶさたに携帯をいじる。
あ、メールだ。
マナーモードにしていて気づかなかったが、バスに乗っている間に、文ちゃんからメールがきていた。
『映画、おもしろかったかな?
昨日のカラオケ、美央っちがこれなくて 二人とも残念がってたヨ。
今度こそ、一緒に行こうね』
絵文字まじりの短い文面に目を走らせて、アタシはハッとした。
しまった! 映画!
今日から公開だったのに。あんなに前から楽しみにしていたのを、すっかり忘れてしまうなんて。
何やってんだろ、アタシ……。
今日、この後で観に行ってもよかったけれど、あいにく、チケットは家に置いてきてしまった。
『急な用事で、観に行けなかったよ。
来週のお楽しみになっちゃった。
カラオケ、アタシも行きたかったなぁ。
ホント残念! また誘ってね!』
とり急ぎ返信メールを送り、アタシは携帯をしまった。
どうして忘れたのかは、考えるまでもない。アタシは、その元凶に目を移した。
赤いビールケースを両手に二個ずつ持った一之瀬が、子供たちにとり囲まれながらやって来る。
もしかして、バイト先から借りてきたんだろうか? 何らかのマジックに必要なのだろうが、一体、何に使うと言って借りたのだろう? それとも、バイト仲間たちは知っているんだろうか? 彼がストリートマジシャンであることを。
この街の景色と同様、一之瀬にもたくさんの顔がある。学食でつまらなさそうに食事していた高校生の顔、苦手な作業も一生懸命がんばっている店員の顔。そして、子供相手でも手をぬかない、パフォーマーの顔。どれも、違う時間、違う場所で見るからこそ、出会える顔だ。
映画を公開初日に観られなかったのは残念だったけれど、後悔というほどではなかった。
この日、この場所で、たった一度しか観られないショーと重なってしまったのだから、こちらを選ばないわけにはいかない。
*
四個のビールケースは、演台に化けた。黒いテーブルクロスがかけられて、それらしく整えられている。
「さて、始めようか」
オールドブルーのストレートジーンズに、黒地にグレーのストライプが入ったシャツという、簡素な出で立ちの一之瀬は、例のバックパックを演台の脇に置いた。
「あーあ、今日のギャラリーも、お前さんたちだけか。家族も連れてきていい、って言ったのに」
せっかく観に来てくれた子供たちを相手にぼやく一之瀬は、ちょっぴり可愛かった。
アタシは、その拗ねた笑顔に後押しされるように、ベンチから立ち上がった。立ち上がりはしたが、足が前に進まない。この期に及んで、臆病風が吹きだした。
わざわざこのために来たのに、またコソコソ遠くから見て落ちこむ気?
自分で自分を叱りながら、アタシは多分、泣きそうな顔をしていたと思う。
ああ、神様。どうか、アタシに勇気をください。
思わず天を仰いで、また顔を正面に戻したときだった。
オレンジブラウンのレンズ越し、こちらに視線をよこした一之瀬と、しっかり目が合った。そして、奇跡が起きた。
「こんにちは」
いつぞやのように、真っ直ぐにこちらを見つめたまま、一之瀬は微笑んだ。
「あの、実はですね、これから大してすごくもないマジックを披露するんですけど、もし良かったら観ていきませんか?」
あ、もちろん無料です、とつけ足して、アタシの返答を待っている。
ああ、神様!
アタシは、いつの間にか握りしめていた拳をゆるめた。
「えーと、じゃあ、ちょっとだけ……」
声をかけてもらえて、ものすごく嬉しかったくせに、どうしてこんな素っ気ない言葉しか出てこないんだろう。自分のひねくれ具合に、内心ものすごく凹みながら、アタシはうなずいた。せっかく誘ってくれたのに、気を悪くしたかもしれない。
しかし、アタシの杞憂に反して、一之瀬は瞳を輝かせた。
「やった! ありがとうございます!」
こちらがドギマギするくらい満面の笑顔で、さっそく足元のカバンからトランプを取り出す。
「スペシャルゲストをお招きしちゃったからね、今日は、とっておきの技を披露しないと」
独り言ともセールストークともつかない調子でしゃべりながら、一之瀬はトランプを左手に持った。
カードの山を左手だけで二つに分け、これまた器用に片手で回転させると、よくプロのマジシャンがするように、軽く添えていた右の掌に向けて勢い良くカードを落とした。降り始めの夕立のような小気味よい音とともに、カードが見事にシャッフルされる。一度だけでなく、二度、三度と。
「おおぉ!」
子供たちが感嘆のうなり声を上げた。
すごい、綺麗……。
彼の長い指の間を、カードが滝のように流れ落ちていく。その様子に、すっかり見とれていた時だった。
「あ、やべっ」
一之瀬の舌打ちが響いて、先ほどまで片手にぴたりと納まっていたカードが不規則に落下し、彼の足元に無残に広がった。
「ゴメン、滑った」
誰にともなく謝ると、一之瀬は決まり悪そうにそそくさとしゃがみ、カードを拾い集めた。
「何やってんだよ、サトシぃー」
「女子の前だからって、カッコつけるから悪いんだぞ」
子供たちの容赦ない野次が飛ぶ。
下の名前、サトシって言うんだ。っていうか、女子って、アタシのこと?
「誰だ? 今、どさくさにまぎれて、オレのこと呼び捨てにした奴」
カードを拾い終えた一之瀬は、屈んだまま、上目遣いに子供たちを睥睨した。しかし、その頬には微かな赤みがさしていて、照れ隠しのパフォーマンスに過ぎないのがわかってしまった。
「ふふっ」
気づいたときには、笑いをおさえることができなかった。皆の視線が一斉に集まるのを感じたけれど、どうしようもない。
くつくつ笑い続けるアタシにつられるように、子供たちが笑いだした。初めは複雑な顔をしていた一之瀬も、最後には一緒になって笑う。
「ごめんなさい。何か、ツボに入っちゃって」
皆で一しきり笑った後、アタシは一之瀬に詫びた。決して、彼の失敗がおかしかったわけではないのだと、しどろもどろに弁明する。
「別に気にしてないです」
一之瀬はからりと笑った。お客さんが楽しければ結果オーライでしょ、と。
「でも、汚名返上のチャンスはもらわないと」
そう言うなり、彼は再びワンハンドシャッフルでカードを切りなおした。
こうして華麗に技を決める一之瀬は、間違いなくカッコいい。一度でも彼の演技を見たら、例え素人マジシャンであっても、絶対にファンになる人間がいると思った。現に、ここに一人いる。
「さぁ、仕切り直しといきましょうか」
一之瀬には、プロ顔負けの落ち着きと、これから確かに面白いことが始まるのだと、人に期待させる〝何か〟があった。こういう、訓練だけでは身につけられない〝何か〟のことを〝素質〟と呼ぶのかもしれない。
「さて、始めようか」
オールドブルーのストレートジーンズに、黒地にグレーのストライプが入ったシャツという、簡素な出で立ちの一之瀬は、例のバックパックを演台の脇に置いた。
「あーあ、今日のギャラリーも、お前さんたちだけか。家族も連れてきていい、って言ったのに」
せっかく観に来てくれた子供たちを相手にぼやく一之瀬は、ちょっぴり可愛かった。
アタシは、その拗ねた笑顔に後押しされるように、ベンチから立ち上がった。立ち上がりはしたが、足が前に進まない。この期に及んで、臆病風が吹きだした。
わざわざこのために来たのに、またコソコソ遠くから見て落ちこむ気?
自分で自分を叱りながら、アタシは多分、泣きそうな顔をしていたと思う。
ああ、神様。どうか、アタシに勇気をください。
思わず天を仰いで、また顔を正面に戻したときだった。
オレンジブラウンのレンズ越し、こちらに視線をよこした一之瀬と、しっかり目が合った。そして、奇跡が起きた。
「こんにちは」
いつぞやのように、真っ直ぐにこちらを見つめたまま、一之瀬は微笑んだ。
「あの、実はですね、これから大してすごくもないマジックを披露するんですけど、もし良かったら観ていきませんか?」
あ、もちろん無料です、とつけ足して、アタシの返答を待っている。
ああ、神様!
アタシは、いつの間にか握りしめていた拳をゆるめた。
「えーと、じゃあ、ちょっとだけ……」
声をかけてもらえて、ものすごく嬉しかったくせに、どうしてこんな素っ気ない言葉しか出てこないんだろう。自分のひねくれ具合に、内心ものすごく凹みながら、アタシはうなずいた。せっかく誘ってくれたのに、気を悪くしたかもしれない。
しかし、アタシの杞憂に反して、一之瀬は瞳を輝かせた。
「やった! ありがとうございます!」
こちらがドギマギするくらい満面の笑顔で、さっそく足元のカバンからトランプを取り出す。
「スペシャルゲストをお招きしちゃったからね、今日は、とっておきの技を披露しないと」
独り言ともセールストークともつかない調子でしゃべりながら、一之瀬はトランプを左手に持った。
カードの山を左手だけで二つに分け、これまた器用に片手で回転させると、よくプロのマジシャンがするように、軽く添えていた右の掌に向けて勢い良くカードを落とした。降り始めの夕立のような小気味よい音とともに、カードが見事にシャッフルされる。一度だけでなく、二度、三度と。
「おおぉ!」
子供たちが感嘆のうなり声を上げた。
すごい、綺麗……。
彼の長い指の間を、カードが滝のように流れ落ちていく。その様子に、すっかり見とれていた時だった。
「あ、やべっ」
一之瀬の舌打ちが響いて、先ほどまで片手にぴたりと納まっていたカードが不規則に落下し、彼の足元に無残に広がった。
「ゴメン、滑った」
誰にともなく謝ると、一之瀬は決まり悪そうにそそくさとしゃがみ、カードを拾い集めた。
「何やってんだよ、サトシぃー」
「女子の前だからって、カッコつけるから悪いんだぞ」
子供たちの容赦ない野次が飛ぶ。
下の名前、サトシって言うんだ。っていうか、女子って、アタシのこと?
「誰だ? 今、どさくさにまぎれて、オレのこと呼び捨てにした奴」
カードを拾い終えた一之瀬は、屈んだまま、上目遣いに子供たちを睥睨した。しかし、その頬には微かな赤みがさしていて、照れ隠しのパフォーマンスに過ぎないのがわかってしまった。
「ふふっ」
気づいたときには、笑いをおさえることができなかった。皆の視線が一斉に集まるのを感じたけれど、どうしようもない。
くつくつ笑い続けるアタシにつられるように、子供たちが笑いだした。初めは複雑な顔をしていた一之瀬も、最後には一緒になって笑う。
「ごめんなさい。何か、ツボに入っちゃって」
皆で一しきり笑った後、アタシは一之瀬に詫びた。決して、彼の失敗がおかしかったわけではないのだと、しどろもどろに弁明する。
「別に気にしてないです」
一之瀬はからりと笑った。お客さんが楽しければ結果オーライでしょ、と。
「でも、汚名返上のチャンスはもらわないと」
そう言うなり、彼は再びワンハンドシャッフルでカードを切りなおした。
こうして華麗に技を決める一之瀬は、間違いなくカッコいい。一度でも彼の演技を見たら、例え素人マジシャンであっても、絶対にファンになる人間がいると思った。現に、ここに一人いる。
「さぁ、仕切り直しといきましょうか」
一之瀬には、プロ顔負けの落ち着きと、これから確かに面白いことが始まるのだと、人に期待させる〝何か〟があった。こういう、訓練だけでは身につけられない〝何か〟のことを〝素質〟と呼ぶのかもしれない。
- 2010.01.01 -
© 2010 Ao Kamisawa. All Rights Reserved.
- Celeste Blue Kingdom -
- Celeste Blue Kingdom -