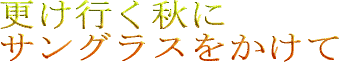Written by Ao Kamisawa.
第 7 話 夢 と薔薇
一日、二十四時間、一定の速度で流れているはずなのに、楽しい時間は、なぜか、あっという間に過ぎていく。
「悪い、もうネタ切れ。今日は、これで勘弁して」
一之瀬はお手上げと言わんばかりに、カードを演台の上に放った。
子供たちの延々と続くリクエストに従い、実に二時間、彼はカードマジックのレパートリーを披露し続けた。そりゃ、ネタも尽きるだろう。
「じゃあ、他のやつ見せてよ。コインとか輪ゴムとか使うやつ」
「あのなぁ、オレ、この二時間、ずっとしゃべりっぱなしなんだぞ? 少しは休ませろよ」
子供たちの過酷な要求を、一之瀬は速攻で拒否した。
「ちぇっ、体力ないなぁ」
「じゃあ、一〇分だけ休んでいいよ。その間、オレ達、ドッジしてるから」
「はいはい。寛大なお心遣い、痛みいります」
小学生相手に皮肉で返すと、一之瀬はふいに真顔になってこちらに向き直った。
「すみません。ちょっとだけ、小休止させてください」
軽く片手を上げ、鉄棒横のベンチにドサリと腰を落とす。繊細な演技の連続で、相当疲れているようだ。
アタシは辺りに視線を巡らせた。公衆トイレの近くに、自販機が見える。
「あの、何か飲みませんか?」
アタシはバッグから財布を取り出しながら尋ねた。
「お礼に、奢らせてください」
「いや、礼なんていいです!」
一之瀬は、とんでもない、とばかりに、大きく頭をふった。
「オレの方からお誘いしたわけだし、それに、気がつけば、こんなに長いことつき合わせてしまって……。その、今さらだけど、お時間、大丈夫でしたか?」
「もちろん」
アタシは言下にうなずいた。
「こちらこそ、時間を忘れて楽しませていただいて、ありがとうございました。リクエストがないなら、適当に買ってきて無理やり感謝の気持ちを押しつけますけど、いいですか?」
お汁粉のホットを買ってきても知りませんよ? と、軽く脅迫する。アタシだって、何かお礼をしないと気がすまない。
お汁粉は嫌だな、と小さく吹き出し、一之瀬は寛いだ表情になった。
「それじゃあ、お言葉に甘えて、コーラを」
「了解」
右手でOKのサインを作ると、アタシは自販機まで小走りした。ゆっくり歩いてなんて、いられなかった。
「悪い、もうネタ切れ。今日は、これで勘弁して」
一之瀬はお手上げと言わんばかりに、カードを演台の上に放った。
子供たちの延々と続くリクエストに従い、実に二時間、彼はカードマジックのレパートリーを披露し続けた。そりゃ、ネタも尽きるだろう。
「じゃあ、他のやつ見せてよ。コインとか輪ゴムとか使うやつ」
「あのなぁ、オレ、この二時間、ずっとしゃべりっぱなしなんだぞ? 少しは休ませろよ」
子供たちの過酷な要求を、一之瀬は速攻で拒否した。
「ちぇっ、体力ないなぁ」
「じゃあ、一〇分だけ休んでいいよ。その間、オレ達、ドッジしてるから」
「はいはい。寛大なお心遣い、痛みいります」
小学生相手に皮肉で返すと、一之瀬はふいに真顔になってこちらに向き直った。
「すみません。ちょっとだけ、小休止させてください」
軽く片手を上げ、鉄棒横のベンチにドサリと腰を落とす。繊細な演技の連続で、相当疲れているようだ。
アタシは辺りに視線を巡らせた。公衆トイレの近くに、自販機が見える。
「あの、何か飲みませんか?」
アタシはバッグから財布を取り出しながら尋ねた。
「お礼に、奢らせてください」
「いや、礼なんていいです!」
一之瀬は、とんでもない、とばかりに、大きく頭をふった。
「オレの方からお誘いしたわけだし、それに、気がつけば、こんなに長いことつき合わせてしまって……。その、今さらだけど、お時間、大丈夫でしたか?」
「もちろん」
アタシは言下にうなずいた。
「こちらこそ、時間を忘れて楽しませていただいて、ありがとうございました。リクエストがないなら、適当に買ってきて無理やり感謝の気持ちを押しつけますけど、いいですか?」
お汁粉のホットを買ってきても知りませんよ? と、軽く脅迫する。アタシだって、何かお礼をしないと気がすまない。
お汁粉は嫌だな、と小さく吹き出し、一之瀬は寛いだ表情になった。
「それじゃあ、お言葉に甘えて、コーラを」
「了解」
右手でOKのサインを作ると、アタシは自販機まで小走りした。ゆっくり歩いてなんて、いられなかった。
*
「そう言えば、お客さん、いつもウチのコンビニをご利用いただいてますよね?」
コーラのプルタブを引きながら、一之瀬は何でもないことのように言った。一口飲んで、あー、うまい、と顔をほころばせる。
いきなり核心をつかれて、アタシは動揺した。予期したことではあったけれど、サングラスは変装の一助にもなっていなかった。
「よく、わかりましたね」
「そりゃ、常連のお客様くらいは」
一之瀬は、はにかむような笑顔を浮かべた。
「でも、こんな時間にお会いするとは思いませんでした。今日は、お仕事、お休みですか?」
「え?」
思ってもみなかった質問に、アタシは返答につまった。
「すみません、よけいなこと聞いて。いつも決まって遅い時間にご来店なさるから、ずっと会社帰りかと思ってたんですけど……」
忘れてください、と言って一之瀬は再び缶に口をつけた。
会社帰り……。
期せずして、望みが叶った。週一回、必ず現れるようになったアタシの存在に、一之瀬は気づいていたのだ。そして、その目に映るアタシは、残業明けの勤め人に見えている。
アタシは思わず苦笑した。どうもアタシたちは、お互いを実年齢以上に見ていたらしい。
一之瀬の口ぶりは、完全にアタシを年上だと思っていて、何となく、自分も高校生だと告げるタイミングを逸してしまった。
「あの、マジックは、いつごろから始めたんですか?」
あまり自分のことを話さずにすむよう、アタシは話題を変えた。
「小学一年生からです」
「え、そんなに昔から?」
声のトーンが一オクターブ上がってしまった。そんなに年季が入っていたなんて。
「ええ。昔って言っても、たかだか十年ですけどね」
一之瀬は苦笑いになった。今、高三なんで。
「それじゃあ、今年、受験生?」
アタシはしらばっくれて尋ねた。
ウチの学校の進学率は実に九九・八パーセントだ。現役生の合格率はともかく、受験しない者はまずいない。
「ええ、まぁ……」
一之瀬は歯切れ悪くうなずいた。
「本当は、こんなとこで遊んでる場合じゃないんでしょうけど、練習やめると腕が鈍るから。浪人するより、そっちの方が怖くて……」
そう言って、一之瀬は照れくさそうに微笑んだ。
「オレ、将来、プロのマジシャンになりたいんです」
自分でも夢みたいな夢だと思うけど、と肩をすくめる。
「それじゃあ、今は、受験勉強とバイトとマジックの練習と、三つも掛けもちしてるんですか? 大変じゃありません?」
アタシは首をかしげた。アタシなんて、予備校通いだけでも手一杯な感じなのに。
「んー、確かに忙しいですけど、苦ではないです」
飲み干した空き缶を脇に置くと、一之瀬は両手を組み合わせた。人に見られるために磨かれた、麗しいマジシャンの指。
「マジックって、テクニックだけじゃなくて、道具に頼る部分が大きいから、色んなネタをやろうと思うと、どうしても費用がかかるんです。良い道具を使いたければ、けっこうな値段がするし。だから、マジックを続けている限り、バイトは欠かせないんです」
まぁ、お金の問題はプロになれれば解決するんでしょうけど、と言って、一之瀬は微苦笑を浮かべた。
「今はご覧の通り修行中で、子供相手に練習の成果を披露してるだけだけど、本当は子供だけじゃなくて、色んな世代の人に見てもらいたいんですよね。でも、大人は忙しいし、得体の知れないストリートマジシャンなんて、ぜんぜん眼中になくて。っていうか、むしろ敵視? ま、そんなわけで、とりあえずギャラリーを集められるようになることが、今の目標です」
「そう……」
叶うといいですね、と感慨をこめて返しながらも、アタシは胸の奥が重たくなるのを感じた。
彼のマジックは、単なる趣味ではなかったのだ。校則違反というリスクを負ってまでも守りたい、大切な夢。
一之瀬にも大きな夢があったのだ。大きすぎて、ある意味とても子供じみた理想像。アタシにはとても描けない、夢のある未来。
でも、彼には叶えられる可能性があると思う。テレビで活躍するようなビッグスターとまではいかなくとも、小さな会場で観客を喜ばせることなら充分できる。たった今、アタシたちを楽しませてくれたように。
彼は、確かに特別な才能を持っている。一度は身近に思えた一之瀬が、再び遠い存在に戻った気がした。
「あ、そうだ!」
会話が途切れたとき、いきなり、一之瀬が立ち上がった。驚いて顔を上げたアタシの正面に回り、一礼する。
「遅くなりましたが、オレ、一之瀬諭と申します。あの、お客さんのお名前は……?」
「え、ああ、浅川です。浅川美央」
つられて、アタシも腰を上げた。こうして真正面から向き合った一之瀬は、思いのほか大きかった。アタシより一〇センチは高いから、恐らく一七五センチ以上あるだろう。
「ご馳走さまでした、美央さん」
にっこり笑った一之瀬は、お返しに、と言って、何も持っていなかったはずの掌から小さな造花を出して、アタシにくれた。淡いピンクの薔薇の花。
キザなことをする、と思った。他人がされているのを見たら、ぜったい冷笑するだろう、とも。でも、現金なことに、自分がされる分には、ものすごく嬉しい。
「ありがとうございます」
アタシはもらった花を掌に載せて、いつまでも眺めていた。
コーラのプルタブを引きながら、一之瀬は何でもないことのように言った。一口飲んで、あー、うまい、と顔をほころばせる。
いきなり核心をつかれて、アタシは動揺した。予期したことではあったけれど、サングラスは変装の一助にもなっていなかった。
「よく、わかりましたね」
「そりゃ、常連のお客様くらいは」
一之瀬は、はにかむような笑顔を浮かべた。
「でも、こんな時間にお会いするとは思いませんでした。今日は、お仕事、お休みですか?」
「え?」
思ってもみなかった質問に、アタシは返答につまった。
「すみません、よけいなこと聞いて。いつも決まって遅い時間にご来店なさるから、ずっと会社帰りかと思ってたんですけど……」
忘れてください、と言って一之瀬は再び缶に口をつけた。
会社帰り……。
期せずして、望みが叶った。週一回、必ず現れるようになったアタシの存在に、一之瀬は気づいていたのだ。そして、その目に映るアタシは、残業明けの勤め人に見えている。
アタシは思わず苦笑した。どうもアタシたちは、お互いを実年齢以上に見ていたらしい。
一之瀬の口ぶりは、完全にアタシを年上だと思っていて、何となく、自分も高校生だと告げるタイミングを逸してしまった。
「あの、マジックは、いつごろから始めたんですか?」
あまり自分のことを話さずにすむよう、アタシは話題を変えた。
「小学一年生からです」
「え、そんなに昔から?」
声のトーンが一オクターブ上がってしまった。そんなに年季が入っていたなんて。
「ええ。昔って言っても、たかだか十年ですけどね」
一之瀬は苦笑いになった。今、高三なんで。
「それじゃあ、今年、受験生?」
アタシはしらばっくれて尋ねた。
ウチの学校の進学率は実に九九・八パーセントだ。現役生の合格率はともかく、受験しない者はまずいない。
「ええ、まぁ……」
一之瀬は歯切れ悪くうなずいた。
「本当は、こんなとこで遊んでる場合じゃないんでしょうけど、練習やめると腕が鈍るから。浪人するより、そっちの方が怖くて……」
そう言って、一之瀬は照れくさそうに微笑んだ。
「オレ、将来、プロのマジシャンになりたいんです」
自分でも夢みたいな夢だと思うけど、と肩をすくめる。
「それじゃあ、今は、受験勉強とバイトとマジックの練習と、三つも掛けもちしてるんですか? 大変じゃありません?」
アタシは首をかしげた。アタシなんて、予備校通いだけでも手一杯な感じなのに。
「んー、確かに忙しいですけど、苦ではないです」
飲み干した空き缶を脇に置くと、一之瀬は両手を組み合わせた。人に見られるために磨かれた、麗しいマジシャンの指。
「マジックって、テクニックだけじゃなくて、道具に頼る部分が大きいから、色んなネタをやろうと思うと、どうしても費用がかかるんです。良い道具を使いたければ、けっこうな値段がするし。だから、マジックを続けている限り、バイトは欠かせないんです」
まぁ、お金の問題はプロになれれば解決するんでしょうけど、と言って、一之瀬は微苦笑を浮かべた。
「今はご覧の通り修行中で、子供相手に練習の成果を披露してるだけだけど、本当は子供だけじゃなくて、色んな世代の人に見てもらいたいんですよね。でも、大人は忙しいし、得体の知れないストリートマジシャンなんて、ぜんぜん眼中になくて。っていうか、むしろ敵視? ま、そんなわけで、とりあえずギャラリーを集められるようになることが、今の目標です」
「そう……」
叶うといいですね、と感慨をこめて返しながらも、アタシは胸の奥が重たくなるのを感じた。
彼のマジックは、単なる趣味ではなかったのだ。校則違反というリスクを負ってまでも守りたい、大切な夢。
一之瀬にも大きな夢があったのだ。大きすぎて、ある意味とても子供じみた理想像。アタシにはとても描けない、夢のある未来。
でも、彼には叶えられる可能性があると思う。テレビで活躍するようなビッグスターとまではいかなくとも、小さな会場で観客を喜ばせることなら充分できる。たった今、アタシたちを楽しませてくれたように。
彼は、確かに特別な才能を持っている。一度は身近に思えた一之瀬が、再び遠い存在に戻った気がした。
「あ、そうだ!」
会話が途切れたとき、いきなり、一之瀬が立ち上がった。驚いて顔を上げたアタシの正面に回り、一礼する。
「遅くなりましたが、オレ、一之瀬諭と申します。あの、お客さんのお名前は……?」
「え、ああ、浅川です。浅川美央」
つられて、アタシも腰を上げた。こうして真正面から向き合った一之瀬は、思いのほか大きかった。アタシより一〇センチは高いから、恐らく一七五センチ以上あるだろう。
「ご馳走さまでした、美央さん」
にっこり笑った一之瀬は、お返しに、と言って、何も持っていなかったはずの掌から小さな造花を出して、アタシにくれた。淡いピンクの薔薇の花。
キザなことをする、と思った。他人がされているのを見たら、ぜったい冷笑するだろう、とも。でも、現金なことに、自分がされる分には、ものすごく嬉しい。
「ありがとうございます」
アタシはもらった花を掌に載せて、いつまでも眺めていた。
- 2010.01.01 -
© 2010 Ao Kamisawa. All Rights Reserved.
- Celeste Blue Kingdom -
- Celeste Blue Kingdom -