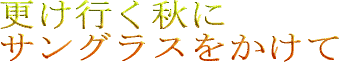Written by Ao Kamisawa.
第 8 話 季節 はずれのサクラ、咲 く?
右手に持っていた小さなボールが、一瞬にして左手に移る。一つしかなかったはずのそれは、いつの間にやら、二つ、三つと増えていき、そうかと思うと、瞬く間に消失する。
一之瀬の掌は異次元とつながっている。いつだったか、常連の小学生が真顔で言ったのを思い出し、アタシは小さく笑った。
「なに思い出し笑いしてるんですか?」
スポンジ製のボールをジャグリングの要領で玩びながら、一之瀬がすかさずツッコミをよこす。やらしいなぁ、と。
「そうよ。やらしいこと考えてたんだから」
アタシが澄まして返すと、彼はギョッとしたように目をむき、たちまち赤くなった。自分からキワドイ冗談を持ち出すくせに、同じテンションで切り替えされると、何も言い返せなくなるのだから笑ってしまう。照れるくらいなら、言わなきゃいいのに。
「バーカ、冗談に決まってるでしょ」
笑って、アタシはベンチを立った。いつもの特等席――ビールケースの真正面にスタンバイして、彼を促す。
「そろそろ、始めましょう?」
一之瀬の掌は異次元とつながっている。いつだったか、常連の小学生が真顔で言ったのを思い出し、アタシは小さく笑った。
「なに思い出し笑いしてるんですか?」
スポンジ製のボールをジャグリングの要領で玩びながら、一之瀬がすかさずツッコミをよこす。やらしいなぁ、と。
「そうよ。やらしいこと考えてたんだから」
アタシが澄まして返すと、彼はギョッとしたように目をむき、たちまち赤くなった。自分からキワドイ冗談を持ち出すくせに、同じテンションで切り替えされると、何も言い返せなくなるのだから笑ってしまう。照れるくらいなら、言わなきゃいいのに。
「バーカ、冗談に決まってるでしょ」
笑って、アタシはベンチを立った。いつもの特等席――ビールケースの真正面にスタンバイして、彼を促す。
「そろそろ、始めましょう?」
*
初めて一之瀬のマジックを見たあの土曜日から、間もなく一月が経とうとしていた。
あの日、彼はバイトのない平日と毎週土曜日に、この公園でパフォーマンスをしていると言った。それから、もし暇だったら、また観にきてほしい、と。
すっかり一之瀬のファンになったアタシは、土曜日は必ず、平日も予備校のない日はできる限り、この公園に通いつめた。
しかし、彼のシフトがわからないので、せっかく来たのに空振りに終わることも少なくなかった。でも、だからといって、彼と連絡先を交換したり、事前に予定を確認するようなことはしなかった。
そんな日は、この公園や近くの公立図書館で適当に時間をつぶした後、例のコンビニに寄ってみる。そこで一之瀬に会えれば、シュークリームを買って帰る。会えなくても、気晴らしにシュークリームを買って帰る。
その一方で、学校にいる間は彼に遭遇しないよう、細心の注意を払った。三年生の教室には決して近づかず、学食や図書室などの共用スペースに行くときは、端っこの目立たない席で、うつむいて過ごす。
一之瀬は未だにアタシに敬意を払い続けてくれているから、今さら後輩であることがバレるのは気まずかった。
それに、アタシにも、学校で過ごしている間の〝違うアタシの顔〟があって、それを一之瀬に見られるのは、どうしても嫌だった。平凡で目立たず、何の面白みもない、普通の女子高生の顔なんて。
だから、このままが良かった。
会いたくても、会えない。もし会えたら、素直に偶然を喜ぶ。
この距離感が心地よいのは、多分、アタシだけではないと思う。
その証拠に、一之瀬はアタシのプライベートに一切触れようとしなかった。最初にした『お仕事、お休みですか?』という、世間話的な質問をのぞいて、ただの一度も。
コンビニの店員と、その客。
マジシャンと、その観客。
一之瀬が望んでいるのは、この関係を壊さないことなのかも知れない。
あの日、彼はバイトのない平日と毎週土曜日に、この公園でパフォーマンスをしていると言った。それから、もし暇だったら、また観にきてほしい、と。
すっかり一之瀬のファンになったアタシは、土曜日は必ず、平日も予備校のない日はできる限り、この公園に通いつめた。
しかし、彼のシフトがわからないので、せっかく来たのに空振りに終わることも少なくなかった。でも、だからといって、彼と連絡先を交換したり、事前に予定を確認するようなことはしなかった。
そんな日は、この公園や近くの公立図書館で適当に時間をつぶした後、例のコンビニに寄ってみる。そこで一之瀬に会えれば、シュークリームを買って帰る。会えなくても、気晴らしにシュークリームを買って帰る。
その一方で、学校にいる間は彼に遭遇しないよう、細心の注意を払った。三年生の教室には決して近づかず、学食や図書室などの共用スペースに行くときは、端っこの目立たない席で、うつむいて過ごす。
一之瀬は未だにアタシに敬意を払い続けてくれているから、今さら後輩であることがバレるのは気まずかった。
それに、アタシにも、学校で過ごしている間の〝違うアタシの顔〟があって、それを一之瀬に見られるのは、どうしても嫌だった。平凡で目立たず、何の面白みもない、普通の女子高生の顔なんて。
だから、このままが良かった。
会いたくても、会えない。もし会えたら、素直に偶然を喜ぶ。
この距離感が心地よいのは、多分、アタシだけではないと思う。
その証拠に、一之瀬はアタシのプライベートに一切触れようとしなかった。最初にした『お仕事、お休みですか?』という、世間話的な質問をのぞいて、ただの一度も。
コンビニの店員と、その客。
マジシャンと、その観客。
一之瀬が望んでいるのは、この関係を壊さないことなのかも知れない。
*
「うそぉ! スゴーイ!」
アタシの心からの感嘆に、通りすがりの人が何事かと目を留める。あと一息だ。
「驚くのは、まだ早いですよ」
一之瀬は得意げに片方の眉だけつり上げると、パチンと指を鳴らした。
その瞬間、翼を広げた鳥の白いお腹が目に飛びこんできて、アタシは度肝をぬかれた。バッサバッサと力強い羽音をたてて上空へ飛び去る鳩の姿を、呆然と見送る。まさか、鳩まで出せるとは。
あんまりビックリしすぎて言葉も出ないアタシに代わって、背後から歓声と拍手が轟いた。振り返ると、けっこうな人数の通行人が足を止め、鳩出現の瞬間を目撃していた。
「どうも!」
大技の成功に気をよくした一之瀬は、満面の笑みで声援に応えると、すかさず次の演技に移った。後ろにできた人だかりは、そのまま動かない。
よし! アタシは小さくうなずくと、そっと特等席を離れた。
アタシが公園に通うようになったのは、もちろん、一之瀬のマジックが好きだからだけれど、自分のためだけではなかった。〝とりあえずギャラリーを集められるようになる〟という、彼の目標達成に手を貸すためだ。
一之瀬は腕が良いのに、なぜ客が寄りつかないのか? 理由を考えたとき、最初に思い浮かんだのはアタシ自身の経験だった。もっと近くで見てみたいけれど、自分以外に客がいない状況では、なかなか声をかけづらい。でも、誰か一人でもいれば、気楽に様子見ができる。
要はサクラがいれば良いのだ。とびきり熱心で、愛のあるサクラが。
幸い、一之瀬のマジックは本物だったから、無理して面白がる必要はなく、自然体でいればよかった。
そして今、この密かな試みは、少しずつ実を結び始めている。そのことが、アタシにささやかな満足感を与えてくれた。
土曜日の昼下がり、快晴。今日は月に一度のフリーマーケットが開かれており、人出も十分だった。絶好のアピール日和。
アタシはサングラスを外して頭に載せると、太陽をふり仰いだ。秋は更け、和らいだ日差しに、季節の移ろいを感じる。
いつか、一之瀬はきっと舞台に立つ。それを、アタシは陰ながら応援するのだ。彼の夢が叶うことが、アタシの喜び。大切な大切な、アタシのマジシャン。
一之瀬の夢こそが、アタシの夢なのだ。
そう思った時、目の前が大きく開けた気がした。アタシにも、夢がある。
アタシの心からの感嘆に、通りすがりの人が何事かと目を留める。あと一息だ。
「驚くのは、まだ早いですよ」
一之瀬は得意げに片方の眉だけつり上げると、パチンと指を鳴らした。
その瞬間、翼を広げた鳥の白いお腹が目に飛びこんできて、アタシは度肝をぬかれた。バッサバッサと力強い羽音をたてて上空へ飛び去る鳩の姿を、呆然と見送る。まさか、鳩まで出せるとは。
あんまりビックリしすぎて言葉も出ないアタシに代わって、背後から歓声と拍手が轟いた。振り返ると、けっこうな人数の通行人が足を止め、鳩出現の瞬間を目撃していた。
「どうも!」
大技の成功に気をよくした一之瀬は、満面の笑みで声援に応えると、すかさず次の演技に移った。後ろにできた人だかりは、そのまま動かない。
よし! アタシは小さくうなずくと、そっと特等席を離れた。
アタシが公園に通うようになったのは、もちろん、一之瀬のマジックが好きだからだけれど、自分のためだけではなかった。〝とりあえずギャラリーを集められるようになる〟という、彼の目標達成に手を貸すためだ。
一之瀬は腕が良いのに、なぜ客が寄りつかないのか? 理由を考えたとき、最初に思い浮かんだのはアタシ自身の経験だった。もっと近くで見てみたいけれど、自分以外に客がいない状況では、なかなか声をかけづらい。でも、誰か一人でもいれば、気楽に様子見ができる。
要はサクラがいれば良いのだ。とびきり熱心で、愛のあるサクラが。
幸い、一之瀬のマジックは本物だったから、無理して面白がる必要はなく、自然体でいればよかった。
そして今、この密かな試みは、少しずつ実を結び始めている。そのことが、アタシにささやかな満足感を与えてくれた。
土曜日の昼下がり、快晴。今日は月に一度のフリーマーケットが開かれており、人出も十分だった。絶好のアピール日和。
アタシはサングラスを外して頭に載せると、太陽をふり仰いだ。秋は更け、和らいだ日差しに、季節の移ろいを感じる。
いつか、一之瀬はきっと舞台に立つ。それを、アタシは陰ながら応援するのだ。彼の夢が叶うことが、アタシの喜び。大切な大切な、アタシのマジシャン。
一之瀬の夢こそが、アタシの夢なのだ。
そう思った時、目の前が大きく開けた気がした。アタシにも、夢がある。
*
「今度、アマチュアの大会に出場してみようと思うんです」
ひと気も消えた夕暮れ、いつもの鉄棒横のベンチに並んで腰かけながら、一之瀬は弾んだ声を出した。今日の成功で、だいぶ自信がついたようだ。
「いよいよ、夢への挑戦だね」
アタシはしみじみ呟いた。言葉にすると、何だか気恥ずかしい。
「これも、全部、美央さんのお陰です。美央さんが来てくれるようになってから、どんどんギャラリーが増えて、今では美央さんが来られない日にも、何人か観に来てくれる人もいるし――」
「え? そうなんですか?」
アタシは思わず口をはさんだ。自分以外の固定客がいたなんて、そんなの知らない。
「ええ。近所のお年寄りとか、中学生の女の子が友達を連れて冷やかしに来るくらいですけど、小学生オンリーよりは大きな進歩です」
そう言って、一之瀬は屈託なく笑ったが、アタシは一緒になって喜んであげられなかった。
〝アタシのマジシャン〟が、いつの間にか〝みんなのマジシャン〟になっていたことに、全く気づかなかった。
まして、そうなることを望んでいたのはアタシ自身だったはずなのに、この息苦しいほどの胸の痛みは、なんなんだろう? 大事にしていたものを、いきなり奪われたような喪失感……。
いや、そんなのは、つまらない感傷だ。
一之瀬の夢は、アタシの夢。
彼の成功が、アタシの……成功?
一瞬、脳裏を過ぎった疑念を、アタシは振り払った。
一之瀬がたくさんの拍手を浴びた瞬間、アタシは確かに幸せだった。その賞賛が全く自分に向けられていなくとも、そんなのは関係ない。陰から支えるということは、そういうことだ。
ただ、一之瀬だけがわかっていてくれればいい。彼さえ、認めてくれれば――。
「本当に、冗談ぬきで、美央さんはオレの幸運の女神です」
ありがとう、と、一之瀬は真面目な顔でアタシを見つめた。彼は時々、聞いているこちらが恥ずかしさで身もだえするほど乙女な発言を、臆面もなく吐くことがある。根っからのヒーロー気質なのだろう。でも今は、それがたまらなく嬉しい。
「ううん、一之瀬君に実力があったからだよ」
アタシは静かに首をふり、うつむいた。涙が出そうになった。
一之瀬は、アタシの想いをきちんと汲んでくれている。アタシがやってきたことは、決して無駄ではない。
その時、アタシは唐突に悟った。
一之瀬が好きだ。
もう、ずいぶん前から、心のどこかでは感じていたけれど、ずっと見ないフリをしてきた。心地よい現状を、このまま維持したくて。
でも、もう見過ごせない。完全に気持ちが傾いてしまった。
アタシは、一之瀬が好きだ。
「美央さん」
やけに近くで名前を呼ばれて、アタシは顔を上げた。すると、すぐ目の前に、一之瀬の唇が見えた。血色のよい、ふくやかな唇。
「これからも、ずっと応援してくれますか?」
低いビブラートのかかった声で、彼が囁く。少しかすれた、緊張した声音。
アタシは黙ってうなずいた。たった一つの予感が、胸を乱す。
キス……されるんだろうか?
そっと目線を上げると、酷く切実な目をした一之瀬と視線が絡まった。こんな風に、強く〝男〟を意識させる彼の表情は初めてで、アタシは慌てて目を逸らした。
それを待っていたように、一之瀬の顔が近づく。
しかし――。
「……ご褒美、もらってもいいですか?」
土壇場で、彼は体を離した。
「今度、オレが出ようとしている大会で、もし入賞できたら、一回だけ、キスさせてください。そしたら、実力以上の力が出せるかもしれない」
途中でやめるのに、かなり無理をしたらしい。情けない顔で、弱々しく笑む。
アタシは先ほどまでの不安と怯えがするりとほどけ、無性に一之瀬が愛おしくなった。
「ご褒美の前払い、してもいいよ?」
冗談めかして――でも、半ば本気で提案すると、一之瀬は面食らったように瞬きした。それから、伸びらかに笑う。
「いえ、楽しみにとっておきます」
だから、絶対に反故にしないでくださいね? と、念を押され、アタシは笑顔で請け負った。一回なんてケチなことを言わずに、二回でも三回でも、好きなだけご褒美をあげたい気分だった。もちろん、そんな大胆なこと、口が裂けても言えないけれど。
「あー、今日も、よく頑張ったなー」
照れ隠しなのか、ベンチから立ち上がり、一之瀬は大きく伸びをした。
その後ろ姿を、アタシは不思議な気持ちで見つめる。ただのコンビニの店員として見ていた彼と、こうして恋に落ちるなんて、夢にも思わなかった。
「日も暮れたし、そろそろ帰りましょうか?」
視線を感じたのか、一之瀬はアタシの方に振り向いた。その眼差しが、うっとりするほど優しくて、胸が苦しくなる。
「うん」
アタシは、こくりとうなずいた。
あってもなくても、どうでもいい。人生において〝必要に迫られない〟もの。
期待されることもなければ、責任を感じることもない。
そんな気楽な存在に、ずっと憧れていた。
それなのに――。
相手を必要とすること、必要とされることで、人間はこんなにも幸福になれるのだということを、アタシは、このとき初めて知った。
ひと気も消えた夕暮れ、いつもの鉄棒横のベンチに並んで腰かけながら、一之瀬は弾んだ声を出した。今日の成功で、だいぶ自信がついたようだ。
「いよいよ、夢への挑戦だね」
アタシはしみじみ呟いた。言葉にすると、何だか気恥ずかしい。
「これも、全部、美央さんのお陰です。美央さんが来てくれるようになってから、どんどんギャラリーが増えて、今では美央さんが来られない日にも、何人か観に来てくれる人もいるし――」
「え? そうなんですか?」
アタシは思わず口をはさんだ。自分以外の固定客がいたなんて、そんなの知らない。
「ええ。近所のお年寄りとか、中学生の女の子が友達を連れて冷やかしに来るくらいですけど、小学生オンリーよりは大きな進歩です」
そう言って、一之瀬は屈託なく笑ったが、アタシは一緒になって喜んであげられなかった。
〝アタシのマジシャン〟が、いつの間にか〝みんなのマジシャン〟になっていたことに、全く気づかなかった。
まして、そうなることを望んでいたのはアタシ自身だったはずなのに、この息苦しいほどの胸の痛みは、なんなんだろう? 大事にしていたものを、いきなり奪われたような喪失感……。
いや、そんなのは、つまらない感傷だ。
一之瀬の夢は、アタシの夢。
彼の成功が、アタシの……成功?
一瞬、脳裏を過ぎった疑念を、アタシは振り払った。
一之瀬がたくさんの拍手を浴びた瞬間、アタシは確かに幸せだった。その賞賛が全く自分に向けられていなくとも、そんなのは関係ない。陰から支えるということは、そういうことだ。
ただ、一之瀬だけがわかっていてくれればいい。彼さえ、認めてくれれば――。
「本当に、冗談ぬきで、美央さんはオレの幸運の女神です」
ありがとう、と、一之瀬は真面目な顔でアタシを見つめた。彼は時々、聞いているこちらが恥ずかしさで身もだえするほど乙女な発言を、臆面もなく吐くことがある。根っからのヒーロー気質なのだろう。でも今は、それがたまらなく嬉しい。
「ううん、一之瀬君に実力があったからだよ」
アタシは静かに首をふり、うつむいた。涙が出そうになった。
一之瀬は、アタシの想いをきちんと汲んでくれている。アタシがやってきたことは、決して無駄ではない。
その時、アタシは唐突に悟った。
一之瀬が好きだ。
もう、ずいぶん前から、心のどこかでは感じていたけれど、ずっと見ないフリをしてきた。心地よい現状を、このまま維持したくて。
でも、もう見過ごせない。完全に気持ちが傾いてしまった。
アタシは、一之瀬が好きだ。
「美央さん」
やけに近くで名前を呼ばれて、アタシは顔を上げた。すると、すぐ目の前に、一之瀬の唇が見えた。血色のよい、ふくやかな唇。
「これからも、ずっと応援してくれますか?」
低いビブラートのかかった声で、彼が囁く。少しかすれた、緊張した声音。
アタシは黙ってうなずいた。たった一つの予感が、胸を乱す。
キス……されるんだろうか?
そっと目線を上げると、酷く切実な目をした一之瀬と視線が絡まった。こんな風に、強く〝男〟を意識させる彼の表情は初めてで、アタシは慌てて目を逸らした。
それを待っていたように、一之瀬の顔が近づく。
しかし――。
「……ご褒美、もらってもいいですか?」
土壇場で、彼は体を離した。
「今度、オレが出ようとしている大会で、もし入賞できたら、一回だけ、キスさせてください。そしたら、実力以上の力が出せるかもしれない」
途中でやめるのに、かなり無理をしたらしい。情けない顔で、弱々しく笑む。
アタシは先ほどまでの不安と怯えがするりとほどけ、無性に一之瀬が愛おしくなった。
「ご褒美の前払い、してもいいよ?」
冗談めかして――でも、半ば本気で提案すると、一之瀬は面食らったように瞬きした。それから、伸びらかに笑う。
「いえ、楽しみにとっておきます」
だから、絶対に反故にしないでくださいね? と、念を押され、アタシは笑顔で請け負った。一回なんてケチなことを言わずに、二回でも三回でも、好きなだけご褒美をあげたい気分だった。もちろん、そんな大胆なこと、口が裂けても言えないけれど。
「あー、今日も、よく頑張ったなー」
照れ隠しなのか、ベンチから立ち上がり、一之瀬は大きく伸びをした。
その後ろ姿を、アタシは不思議な気持ちで見つめる。ただのコンビニの店員として見ていた彼と、こうして恋に落ちるなんて、夢にも思わなかった。
「日も暮れたし、そろそろ帰りましょうか?」
視線を感じたのか、一之瀬はアタシの方に振り向いた。その眼差しが、うっとりするほど優しくて、胸が苦しくなる。
「うん」
アタシは、こくりとうなずいた。
あってもなくても、どうでもいい。人生において〝必要に迫られない〟もの。
期待されることもなければ、責任を感じることもない。
そんな気楽な存在に、ずっと憧れていた。
それなのに――。
相手を必要とすること、必要とされることで、人間はこんなにも幸福になれるのだということを、アタシは、このとき初めて知った。
- 2010.01.01 -
© 2010 Ao Kamisawa. All Rights Reserved.
- Celeste Blue Kingdom -
- Celeste Blue Kingdom -