ブラインド越しに差し込む西日が、飴色のテーブルにしましまの影を落とす。
放課後の図書室は平穏の一言につきる。静かにページを繰る音、書架を巡る乾いた足音。
この静寂を、アタシは間違いなく愛していた。久しぶりに訪れて、改めて実感する。
でも、もの足りない。
ページを開いたものの、全く読む気になれない本格ミステリを脇に押しやり、アタシは机の上に突っ伏した。
一之瀬とケンカ別れしてから、丸二週間になる。その間、アタシは公園にも、コンビニにも、一度も顔を出さなかった。
両親の手前、予備校だけは行っているけれど、帰りはバス停へ直行し、約三〇分間、ただ突っ立ったままバスが来るのを待っていた。十一月も下旬を過ぎ、寒さが身にしみた。
毎日、一之瀬に会いたかった。
彼の大きな手から、ボールや、造花や、白い鳩が飛び出す様を、繰り返し思い出す。
その内、謝りにいこうとは思っていた。もう、好きだとは言ってもらえなくても、人として最低限の礼儀は尽くさなければならない。
だけど、まだダメだ。時が満ちていない。
アタシは今、一之瀬の存在しない日常で、自分と対峙し続けている。
本当にやりたいことは何なのか?
生きている意味とは?
〝これ〟を取り上げられるくらいだったら、死んだ方がマシだと思えることに、アタシは未だ出会えていない。いや、そもそも、今生きている大人たちの内、一体どれくらいの人が〝これ〟ってやつを持っているんだろう?
自分の身の周りを思い返してみても、そんな大人は見たことがない。皆、日々の暮らしを継続することに精一杯で、生きがいだとか、ポリシーだとかにまで、思いが到ってないように見える。
もしかすると、一之瀬みたいに〝これ〟ってやつを見つけられる人間の方が稀で、そういう人たちは、とっても幸せな人種なのではなかろうか?
やっぱりアタシには、一生かかっても見つけられないかもしれない……。
机に伏せたまま、暗澹とした気持ちでいると、ふいに日差しが遮られ、向かいの席に誰か掛けたのがわかった。
他にも空いてる席があるのに、何で、わざわざアタシの前に座るのよ。
日向ぼっこを邪魔されムカついたアタシは、相手の顔を見てやろうと思って、机の上で組んだ腕の隙間から、ちらりと顔をのぞかせた。逆光に目を細め、ピントを合わせたところで、慌てて元の体勢に戻る。
冬服姿の男子――チャコールグレイのブレザーに、シアンブルーのネクタイをラフに締めた一之瀬が、目の前で頬杖をついていた。
直感的に悟った。
こんな偶然、あるわけがない。彼は、アタシに会いにきたのだ。
「お目覚めですか?」
案の定、一之瀬の淡々とした声が降ってきて、アタシは腹をくくった。のっそりと体を起こし、彼と向き合う。何と言ったらいいのかわからず、じっと黙したまま。
「お久しぶりです」
目が合うと、彼は寂しげな微笑を浮かべた。
「美央さんが来てくれなくなったから、会いにきてしまいました」
ルール違反だと思ったけど、と目を伏せる。
ルール違反?
「……とりあえず、場所を変えましょう」
アタシは本を書架に戻すと、先に立って図書室を後にした。
*
屋上に出ると、冷たい風がボックスプリーツの裾を揺らした。むき出しの腿が、寒さでピリリと引き締まる。
一之瀬は、例のバックパックを足元に投げ出すと、ところどころ塗装のはげた灰色のフェンスに指を絡ませ、グラウンドを見下ろしている。遠く、ホイッスルが響いた。
「いつから気づいてたんですか? アタシが同じ学校の後輩だってこと」
アタシは、一之瀬の後ろ姿に話しかけた。
「十月の半ばくらいだったかな? 全校集会があったでしょう? 初めて見かけたのは、その時です。あとは、学食とか購買の近くで、友達と一緒にいるところを何度か……」
振り向いた彼は、今度は柵にもたれかかった。金網が小さく軋む。
「そんなに前から気づいてたのに、どうして知らんぷりしてたんですか?」
「美央さんが、望んでないと思ったから」
一之瀬は即答した。
「まさか同じ学校だとは思わなかったけど、美央さんが高校生だってことは、校内で見かけるより前に知ってたんです。バイトに行く途中で、美央さんが予備校に入っていくのを見かけたことがあったから。その時は、正直、ビックリしましたよ。美央さんのこと、勝手に社会人だと思い込んでたから。よっぽど声かけようかと思ったけど、最初に話した時に、何となく美央さん、自分のこと話したがらない雰囲気だったから、止めたんです。気まずい思いをさせて、二度と来てもらえなくなったら困るから」
だから、ルールを決めたのだ、と、彼は言う。アタシの口から話が出るまで、決して自分からプライベートな話を聞き出すことはしない。学校で見かけても、気づかないフリをし続けよう、と。
その言葉を聞いて、アタシは急速に力がぬけるのを感じた。あの距離を好もしく思っていたのは、アタシだけだったのだ。
今まで、自分は何と無駄な努力をしていたのだろう。彼に気づかれないようにしていたつもりが、完全にバレていたばかりか、むしろ気遣ってもらっていたなんて。
やっぱり、アタシはぬけている。全然、しっかりなんてしていない。
「今日、ルールを破ってまで会いにきたのは、どうしても美央さんに報告しておきたいことがあったからなんです」
相変わらずの敬語で、一之瀬は続けた。おもむろに、バックパックから黒い筒を取り出し、中からクリーム色の紙を引っぱり出す。それは、賞状だった。
「先週、大会に出場してきました。本当は美央さんに観に来てもらいたかったけど、あんな別れ方をした後で、とても誘う勇気が湧きませんでした。八位入賞です」
アタシの方に賞状を見せながら、しかし、一之瀬は不本意そうに唇を引き結んだ。
「本当は最優秀賞をもらって、美央さんを驚愕させる予定だったんですけど、現実は甘くないですね」
すぐさま、くるくると賞状を筒に戻し、苦笑いになる。幸運の女神を怒らせちゃったのが運の尽きだったかな、と。
「……ごめんなさい」
アタシは深々と頭を下げた。どうしようもない寂しさが、胸を突き上げた。
今まで、あんなに一生懸命応援してきた一之瀬の最初の晴れ舞台を、アタシは、どうして見逃す羽目に陥ったのだろう? どこで道順を誤ったのかといえば、最初からだった。最初から、自分を飾ろうなんて思わずに、素直に、ありのままの自分を見てもらっていれば、こんなことにはならなかったのだ。
「今の女神うんぬんは、冗談ですってば! 顔を上げて――」
「ううん。ちゃんと謝らせて」
慌てて肩に添えられた一之瀬の手を、そっと押しとどめ、アタシは首を振った。
「今まで、本当のこと黙ってて、ごめんなさい。一之瀬君と違って、何の取柄もない、つまらない女子高生だって知られるのが嫌だったの。嫌われるんじゃないかと思って、怖かった……。アタシも、一之瀬君が好きだから。それなのに、この前は真実を打ち明けるつもりが、夢の話で逆ギレまでして……。本当に、ごめんなさい」
首を垂れたまま、もう一度、心からの謝罪をくり返す。
「顔――上げてください」
ふいに、一之瀬の声が柔らかくなった。おずおずと姿勢を戻すと、彼は、ほとんど愉快と言ってもいいくらいの笑顔でアタシを見ていた。
「美央さんは、全然つまらなくないですよ」
軽やかに言う。
「どうして、自分をそんなに過小評価してるのか、オレにはわからないです。美央さんは〝しっかりしてる〟って言われるのが嫌みたいだけど、それって、すごいホメ言葉だと思いませんか? 将来の夢なんて、規模はともかく、遅かれ早かれ、誰にでも見つけられるけど、堅実で信頼されるような人間には、誰もがなれるわけじゃない」
「でも、堅実ってことは、保守的で面白みがないってことでしょう? それよりは、大きな夢を掲げて努力してる人の方が、よっぽど偉いし、素敵だと思う」
「オレは、そうは思いませんよ」
一之瀬は穏やかな口調で反論した。
「夢を持っているからといって、それは必ず叶うわけじゃない。オレの夢なんて、叶わない確率の方が遥かに高いですしね。でも、それでも、オレはマジックが好きだから、絶対にやめないし、やめられないんです。努力しているのも、自分の好きなことのためであって、誰のためでもない。そんな利己的な人間が偉いなんて、オレにはとても思えない」
彼の言いたいことは、わかる。
しかし、そんな風に、決して〝やめない〟と宣言できる強さこそが、アタシの求めているものなのだ。迷うことのない、揺るがない強さ。夢を持つもの特有の、絶対的な強さ。
「納得できないって顔してますね」
一之瀬は相変わらず愉しげに苦笑した。
「美央さんは、夢を崇高なものだと思いこみすぎなんですよ。大体、夢なんてものは、勝手に〝見てしまう〟ものであって、無理して〝見つける〟ものじゃないでしょう?」
事も無げに言われた瞬間、アタシは自分でも驚くほど、ストンと得心がいった。
元来、探すべきでないものを探そうとしていたから、いつまで経っても見つからないのか! 目から鱗だ。
夢とは、酷く利己的なものだと、一之瀬は言った。自分だけが好きで、自分にとって必要であれば、それでいい。
まるで、秋のサングラス。
夏が終わり、日差しを遮る必要がなくなっても、それをかけたいと自分が思うなら、堂々とかけ続ければいいのだ。誰に何を言われても、そんなの関係ない。他人にとって不要なものが、必ずしも自分に当てはまるとは限らない。
だが、それでも残るのは〝いつ見つかるのか?〟という、先の見えない不安感――。
「大丈夫。焦らなくても、そのうち見つかりますよ」
アタシの気持ちを読んだかのようなタイミングで、一之瀬は断言した。何の根拠もないはずなのに、彼が言うと、本当に大丈夫な気がするから不思議だ。それに――。
「だから、それまでは、オレの夢でも一緒に見てましょう? 自分の夢が見つかるまでの〝つなぎ〟だと思って。どうせ同じ時間を過ごすなら、ハラハラ気をもむより、気長に、心穏やかに過ごした方が楽しいですよ」
フォローも万全だ。全く、一之瀬は優しい。
「ありがとう」
アタシは一番シンプルな言葉を、心をこめて発音した。どんなに言葉を尽くしても、この感謝の気持ちは、とても伝えきれない。
焦らなくていい。
アタシは、アタシのペースで進もう。一之瀬と同じ道ではなく、彼と並行していける、別の道を通って。
「えーと、ところで美央さん、実は、もう一つ用事があるんですけど……」
さっきまで、めちゃめちゃ男前だった一之瀬は、急にそわそわし始めた。
「オレとの約束、覚えてますか?」
ポケットに両手をつっこみ、視線を落とす。
「約束……?」
アタシは眉を寄せた。何だったっけ?
「ほら、オレが大会で入賞した暁には……」
「あ!」
思い出した。と、口を開くより早く、我が意を得たり、とばかりに笑った一之瀬に、唇をふさがれた。
初めて触れた、他人の唇。その熱と柔らかさに、恍惚というよりは新鮮な驚きを覚える。
ご褒美がほしいと言われていたけれど、アタシは、それを与えているのか、与えられているのか、良くわからなくなった。
長く短いキスの後、いつの間に閉じたのかさえ覚えていない瞼を薄っすら持ち上げると、一之瀬の潤んだ瞳が飛びこんできた。
「ありがとう、美央さん」
くすぐったくなるような甘い声で、彼は囁く。美央さんとの約束を信じていたから頑張れた、と。
「バカ」
ふっと、笑みがこぼれた。一之瀬の腕の中、互いに見つめ合ったまま、くすくす笑う。
「それにしても、優勝したら、なんてカッコつけてなくてホント良かったぁー。ギリギリ入賞でしたからね。ハードル、低く設定しておいて大正解!」
そんな風にはしゃぐ一之瀬は、高校生でも、店員でも、マジシャンでもない顔をしていた。
それは多分、アタシの前でしか見せない、アタシだけの恋人の顔。
茜色からスミレ色に変わった空を、アタシは、そっと仰ぎ見た。
更け行く秋が、初冬に姿を変えた宵。南の空に輝くオリオン座の下で、アタシたちは幸福な寒さに震えていた。
終 - 2010.01.01 -
INFORMATION
『更け行く秋にサングラスをかけて』は、いかがでしたか?
よろしければ、感想をお聞かせ下さい。一言感想、大歓迎です!
あなたの愛ある一言が、作者の原動力になります!
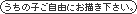
うちの子も、ぜひ描いてやって下さいまし☆ ⇒
絵板

ネット小説ランキングに投票
* 執筆の励みになりますので、ぜひポチッと!