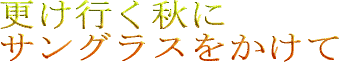Written by Ao Kamisawa.
第 10 話 転 がる
一之瀬に本当のことを打ち明けようと決めてから、四日後。アタシはようやく、彼を公園に呼び出すことに成功した。
一昨日の水曜日、予備校の帰りにコンビニに寄ると、一之瀬はレジにいた。いつも通りシュークリームを選び、会計をしてもらっている間、アタシは勇気を出して尋ねた。
『今度、いつ会えるかな?』
話したいことがあるの、と囁くように続けると、一之瀬は一瞬、驚いた顔をした。
『明後日の夕方は、いつも通り公園に行くつもりでしたけど……』
こんな風に予定を確認したのは初めてのことで、不審に思ったのかもしれない。どうかしたんですか? と、直ぐにも話を聞き出そうとする彼を、急ぎじゃないから、と何とか宥め、アタシは逃げ去るように店を出た。
あれから今日まで、何と、一日一日が長く感じられたことだろう。
アタシは例のベンチで彼を待ちながら、落ち着かずに何度も時計を見た。一六時二七分。いつ来てもおかしくない時間だった。
「ふぅー……」
無意識に溜め息がもれた時――。
「なんか意味深だなぁー、その溜め息」
いきなり、真後ろから声をかけられ、アタシは凍りついた。心臓が一瞬にして収縮したのがわかる。
「うわ、ごめんなさい!」
声も出ないアタシを見て、一之瀬はうろたえながら正面に回りこんできた。
「そんなに驚くと思わなくて! 大丈夫ですか?」
アタシの前にひざまずき、心配そうに様子を窺う。
「……心臓、一回止まりました」
「ホント、ごめんなさい。えーと、とりあえず、これでも飲んで落ち着いてください」
一緒に飲もうと思って持ってきたんです、と言いながら、一之瀬はビニール袋をガサガサいわせて、ホット用のミニペットボトルをとり出した。アタシの好きな、ミルクティー。
「熱いので、お気をつけて」
言われた瞬間、アタシはペットボトルを倒した時のことを鮮やかに思い出した。初めて、一之瀬と会話らしい会話を交わした日。
「もしかして、覚えてるの?」
「もちろん」
一之瀬は、にっこりした。
「オレ、意外と記憶力いいんです。だから、一昨日の美央さんの表情も、よく覚えてます」
彼の顔にわずかな翳りがさして、アタシは怖気づいた。アタシが、彼を不安にさせている。
何て、切り出したらよいだろう。アタシは渡されたペットボトルを、封を切らぬまま両手で包みこんだ。なるべく、さり気なく核心にたどり着くよう、うまく話をもっていかなければならない。
アタシは覚悟を決め、口を開いた。
「あの、真面目な話、一之瀬君はアタシのこと、どう思ってる?」
「好きです」
あまりにあっさり告白されて、アタシは動揺した。男らしいにも程がある。
「いや、そういう意味じゃなくて! えーと、どこが好きっていうか、アタシのこと、どういう人間だと思ってます?」
「どう、って……」
難しいな、と独り言ち、一之瀬はペットボトルの封を開けた。キリッと、固い音が響く。
「うまく言えないけど……一緒にいると、すごく楽しいです。何気ない言葉のなかに思いやりがあって、気が利いて……。時々、小悪魔か? って思うような大胆発言に翻弄されることもあるけど――」
「それは、一之瀬君が変な冗談ふるからでしょう!」
思わずツッコミを入れると、一之瀬は、そうかなぁ? と、笑いながら続けた。
「とにかく、傍にいてくれるだけで安心できるっていうか、頼もしいっていうか……しっかりした人だなぁ、って思います」
しっかり! ここにきて、やはりこのキーワードが出るのかと、アタシは思わず自嘲した。〝浅川美央〟の、誤った代名詞。
「アタシ、全然しっかりなんかしてない」
期せずして、溜め息がまじった。
「アタシには、何にもないんです。将来の夢とか、やりたいこととか。これが好きだって、胸はって言えるような趣味もないし、何をやっても中途半端で、空っぽで……」
一之瀬は困惑した表情を浮かべながらも、アタシの話を大人しく聞いている。
「でも、一之瀬君と出会って、初めて、夢らしい夢を見つけられたと思う」
アタシは勇気を奮い起こして、一之瀬を見つめた。
「アタシの夢は、一之瀬君がプロのマジシャンになることだよ。今まで応援してきて思ったの。アタシも、ずっと一緒に一之瀬君と同じ夢を追いかけたいって。だから――」
「それはおかしいよ」
だから、もう、一之瀬君に隠し事はしたくないって思ったんです。
本当のアタシは、あなたと同じ、普通の高校生なの。それも、二年生。
もちろん、仕事なんかしてない。
毎週水曜日、遅くまでオフィス街にいるのは、近くに通っている予備校があるから。
ごめんね。
騙すつもりなんてなかったんだけど、一之瀬君と違って、何の取柄もない、ただの女子高生だってバレるのが嫌だったの。
本当に、ごめんなさい。
こんなアタシでも、変わらず好きだと思ってくれますか?
そう続けるはずだったアタシの言葉たちは、一之瀬の固い声に遮られ、霧散した。
「美央さんがオレのことを応援してくれるのは、すごく嬉しいし、本当に感謝してます。いつまでも一緒にいてほしいって、心から思う。でも、オレを応援してくれることと、美央さんが追うべき夢は、ぜんぜん別物だと思うんです」
慎重に言葉を選びながら、彼は続けた。
「もし、オレがプロになれなかったとしても、それはオレの責任だし、オレが独りで挫折すればいいだけだけど、美央さんがオレの夢に乗っかっちゃったら、叶わない夢に、どうケリをつけます? オレをどんなに励まして、支えてくれても、オレの力が及ばないせいで、美央さんの夢まで一生叶わないなんて、そんなの耐えられない」
「それは違うよ! アタシは別に、アタシの分の夢まで背負ってもらおうなんて思ってないもの――」
「わかってます。でも、結果的には、そういうことになるでしょう? 美央さんが望もうと、望むまいと、あなたの夢が叶うかどうかは、オレ次第ってことになる。……それって、本当に美央さんの夢って言えるのかな?」
思い切り痛いところを衝かれ、アタシは返す言葉を失った。即死だった。
「美央さんは、美央さん自身が本当にやりたいことをやるべきだと思います。オレなんかの夢を共有しちゃダメだ」
一之瀬の声は揺るぎがなかった。悲しいくらい、取りつく島がなかった。
わかっている。一之瀬の言っていることは、正しい。アタシは彼に便乗して、甘くて楽しい夢を見たかったのだ。責任もプレッシャーもない、いいとこ取りの夢。そう責められても、仕方がない。
でも――。
「……一之瀬君には、わからないよ」
胸の内にわだかまっていた理不尽な言い分が、一気に膨れ上がった。
言ってはいけない。
自制心が警告したにもかかわらず、言葉は止まらなかった。
「特別な才能があって、大きな夢を見て、真っ直ぐそれに向かって突き進んでいける人に、進むべき道すら見えない人間の気持ちなんて、わかりっこない。アタシの気持ちなんて、絶対にわからない」
吐きすてるように呟いて、アタシは立ち上がった。膝に載せていたペットボトルが滑り落ち、足元を転がっていく。
「今日は、ありがとう」
もう、目茶苦茶だ。
「美央さん? 待ってよ! 話は未だ――」
「サヨナラ!」
引き止めようとして伸ばされた一之瀬の手をすり抜け、アタシは走り出した。一度もふり返らず、全速力で公園を駆けぬける。
何て、嫌な女だろう。自分の言いたいことだけ言って、さっさと立ち去るなんて。
自己嫌悪で胸がふさぐ。
八つ当たりもいいとこだ。きっと、今ごろ彼も呆れてる。
結局、真実を言いそびれてしまったけれど、これで良かったのだと思った。どうせアタシは、一之瀬の傍にいる資格を失ったのだから。
彼の夢にぶら下がるしか能のない、つまらない女だと、自ら暴露したようなものだった。
バス停にたどり着いた時、アタシは初めて後ろを見た。当たり前のことだけど、そこに一之瀬の姿は見当たらない。
一昨日の水曜日、予備校の帰りにコンビニに寄ると、一之瀬はレジにいた。いつも通りシュークリームを選び、会計をしてもらっている間、アタシは勇気を出して尋ねた。
『今度、いつ会えるかな?』
話したいことがあるの、と囁くように続けると、一之瀬は一瞬、驚いた顔をした。
『明後日の夕方は、いつも通り公園に行くつもりでしたけど……』
こんな風に予定を確認したのは初めてのことで、不審に思ったのかもしれない。どうかしたんですか? と、直ぐにも話を聞き出そうとする彼を、急ぎじゃないから、と何とか宥め、アタシは逃げ去るように店を出た。
あれから今日まで、何と、一日一日が長く感じられたことだろう。
アタシは例のベンチで彼を待ちながら、落ち着かずに何度も時計を見た。一六時二七分。いつ来てもおかしくない時間だった。
「ふぅー……」
無意識に溜め息がもれた時――。
「なんか意味深だなぁー、その溜め息」
いきなり、真後ろから声をかけられ、アタシは凍りついた。心臓が一瞬にして収縮したのがわかる。
「うわ、ごめんなさい!」
声も出ないアタシを見て、一之瀬はうろたえながら正面に回りこんできた。
「そんなに驚くと思わなくて! 大丈夫ですか?」
アタシの前にひざまずき、心配そうに様子を窺う。
「……心臓、一回止まりました」
「ホント、ごめんなさい。えーと、とりあえず、これでも飲んで落ち着いてください」
一緒に飲もうと思って持ってきたんです、と言いながら、一之瀬はビニール袋をガサガサいわせて、ホット用のミニペットボトルをとり出した。アタシの好きな、ミルクティー。
「熱いので、お気をつけて」
言われた瞬間、アタシはペットボトルを倒した時のことを鮮やかに思い出した。初めて、一之瀬と会話らしい会話を交わした日。
「もしかして、覚えてるの?」
「もちろん」
一之瀬は、にっこりした。
「オレ、意外と記憶力いいんです。だから、一昨日の美央さんの表情も、よく覚えてます」
彼の顔にわずかな翳りがさして、アタシは怖気づいた。アタシが、彼を不安にさせている。
何て、切り出したらよいだろう。アタシは渡されたペットボトルを、封を切らぬまま両手で包みこんだ。なるべく、さり気なく核心にたどり着くよう、うまく話をもっていかなければならない。
アタシは覚悟を決め、口を開いた。
「あの、真面目な話、一之瀬君はアタシのこと、どう思ってる?」
「好きです」
あまりにあっさり告白されて、アタシは動揺した。男らしいにも程がある。
「いや、そういう意味じゃなくて! えーと、どこが好きっていうか、アタシのこと、どういう人間だと思ってます?」
「どう、って……」
難しいな、と独り言ち、一之瀬はペットボトルの封を開けた。キリッと、固い音が響く。
「うまく言えないけど……一緒にいると、すごく楽しいです。何気ない言葉のなかに思いやりがあって、気が利いて……。時々、小悪魔か? って思うような大胆発言に翻弄されることもあるけど――」
「それは、一之瀬君が変な冗談ふるからでしょう!」
思わずツッコミを入れると、一之瀬は、そうかなぁ? と、笑いながら続けた。
「とにかく、傍にいてくれるだけで安心できるっていうか、頼もしいっていうか……しっかりした人だなぁ、って思います」
しっかり! ここにきて、やはりこのキーワードが出るのかと、アタシは思わず自嘲した。〝浅川美央〟の、誤った代名詞。
「アタシ、全然しっかりなんかしてない」
期せずして、溜め息がまじった。
「アタシには、何にもないんです。将来の夢とか、やりたいこととか。これが好きだって、胸はって言えるような趣味もないし、何をやっても中途半端で、空っぽで……」
一之瀬は困惑した表情を浮かべながらも、アタシの話を大人しく聞いている。
「でも、一之瀬君と出会って、初めて、夢らしい夢を見つけられたと思う」
アタシは勇気を奮い起こして、一之瀬を見つめた。
「アタシの夢は、一之瀬君がプロのマジシャンになることだよ。今まで応援してきて思ったの。アタシも、ずっと一緒に一之瀬君と同じ夢を追いかけたいって。だから――」
「それはおかしいよ」
だから、もう、一之瀬君に隠し事はしたくないって思ったんです。
本当のアタシは、あなたと同じ、普通の高校生なの。それも、二年生。
もちろん、仕事なんかしてない。
毎週水曜日、遅くまでオフィス街にいるのは、近くに通っている予備校があるから。
ごめんね。
騙すつもりなんてなかったんだけど、一之瀬君と違って、何の取柄もない、ただの女子高生だってバレるのが嫌だったの。
本当に、ごめんなさい。
こんなアタシでも、変わらず好きだと思ってくれますか?
そう続けるはずだったアタシの言葉たちは、一之瀬の固い声に遮られ、霧散した。
「美央さんがオレのことを応援してくれるのは、すごく嬉しいし、本当に感謝してます。いつまでも一緒にいてほしいって、心から思う。でも、オレを応援してくれることと、美央さんが追うべき夢は、ぜんぜん別物だと思うんです」
慎重に言葉を選びながら、彼は続けた。
「もし、オレがプロになれなかったとしても、それはオレの責任だし、オレが独りで挫折すればいいだけだけど、美央さんがオレの夢に乗っかっちゃったら、叶わない夢に、どうケリをつけます? オレをどんなに励まして、支えてくれても、オレの力が及ばないせいで、美央さんの夢まで一生叶わないなんて、そんなの耐えられない」
「それは違うよ! アタシは別に、アタシの分の夢まで背負ってもらおうなんて思ってないもの――」
「わかってます。でも、結果的には、そういうことになるでしょう? 美央さんが望もうと、望むまいと、あなたの夢が叶うかどうかは、オレ次第ってことになる。……それって、本当に美央さんの夢って言えるのかな?」
思い切り痛いところを衝かれ、アタシは返す言葉を失った。即死だった。
「美央さんは、美央さん自身が本当にやりたいことをやるべきだと思います。オレなんかの夢を共有しちゃダメだ」
一之瀬の声は揺るぎがなかった。悲しいくらい、取りつく島がなかった。
わかっている。一之瀬の言っていることは、正しい。アタシは彼に便乗して、甘くて楽しい夢を見たかったのだ。責任もプレッシャーもない、いいとこ取りの夢。そう責められても、仕方がない。
でも――。
「……一之瀬君には、わからないよ」
胸の内にわだかまっていた理不尽な言い分が、一気に膨れ上がった。
言ってはいけない。
自制心が警告したにもかかわらず、言葉は止まらなかった。
「特別な才能があって、大きな夢を見て、真っ直ぐそれに向かって突き進んでいける人に、進むべき道すら見えない人間の気持ちなんて、わかりっこない。アタシの気持ちなんて、絶対にわからない」
吐きすてるように呟いて、アタシは立ち上がった。膝に載せていたペットボトルが滑り落ち、足元を転がっていく。
「今日は、ありがとう」
もう、目茶苦茶だ。
「美央さん? 待ってよ! 話は未だ――」
「サヨナラ!」
引き止めようとして伸ばされた一之瀬の手をすり抜け、アタシは走り出した。一度もふり返らず、全速力で公園を駆けぬける。
何て、嫌な女だろう。自分の言いたいことだけ言って、さっさと立ち去るなんて。
自己嫌悪で胸がふさぐ。
八つ当たりもいいとこだ。きっと、今ごろ彼も呆れてる。
結局、真実を言いそびれてしまったけれど、これで良かったのだと思った。どうせアタシは、一之瀬の傍にいる資格を失ったのだから。
彼の夢にぶら下がるしか能のない、つまらない女だと、自ら暴露したようなものだった。
バス停にたどり着いた時、アタシは初めて後ろを見た。当たり前のことだけど、そこに一之瀬の姿は見当たらない。
- 2010.01.01 -
© 2010 Ao Kamisawa. All Rights Reserved.
- Celeste Blue Kingdom -
- Celeste Blue Kingdom -